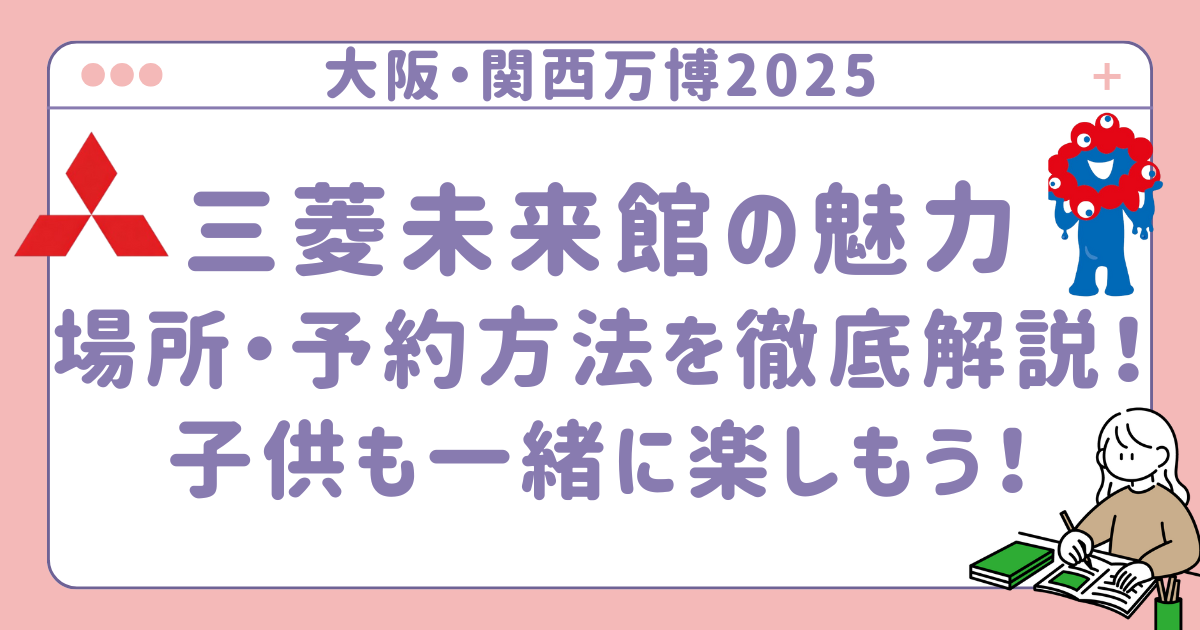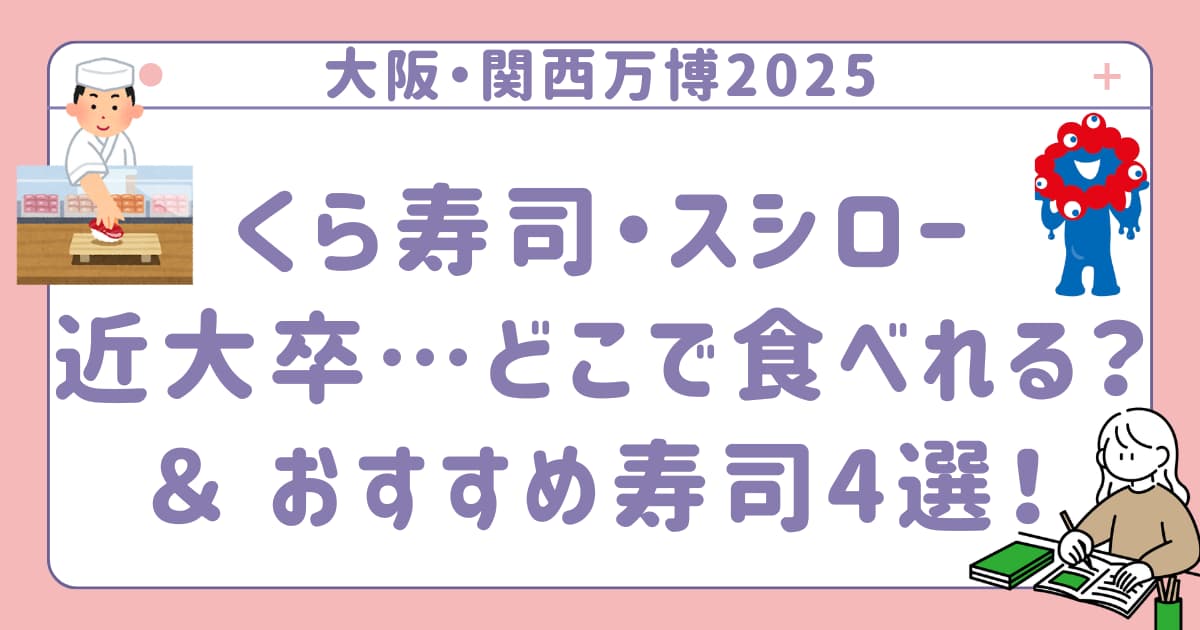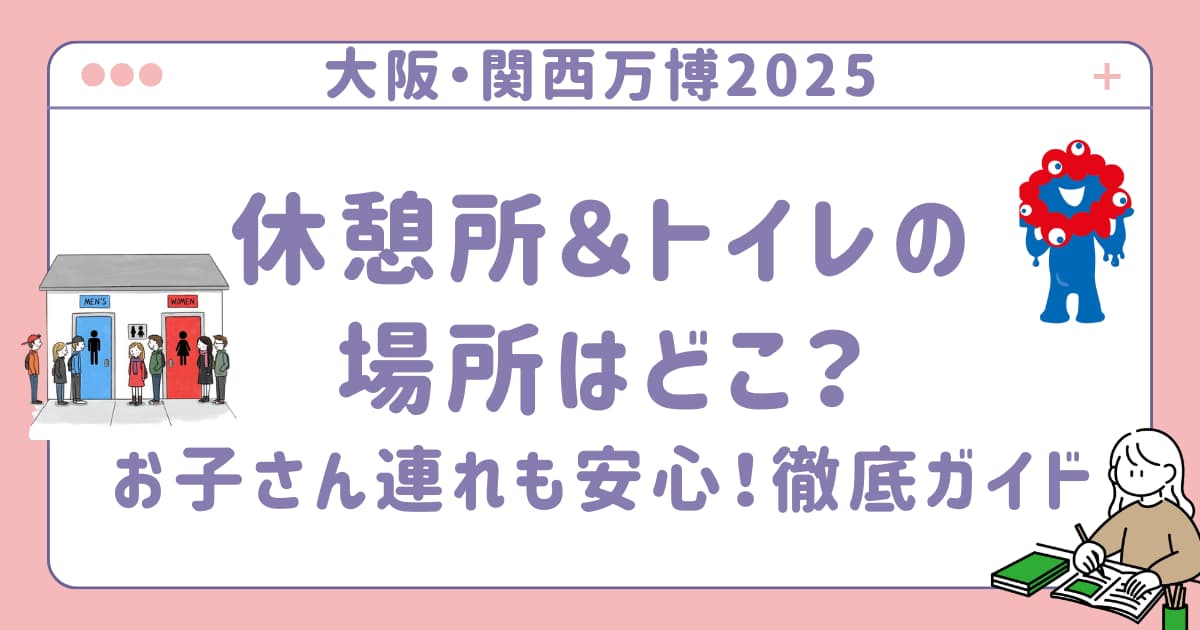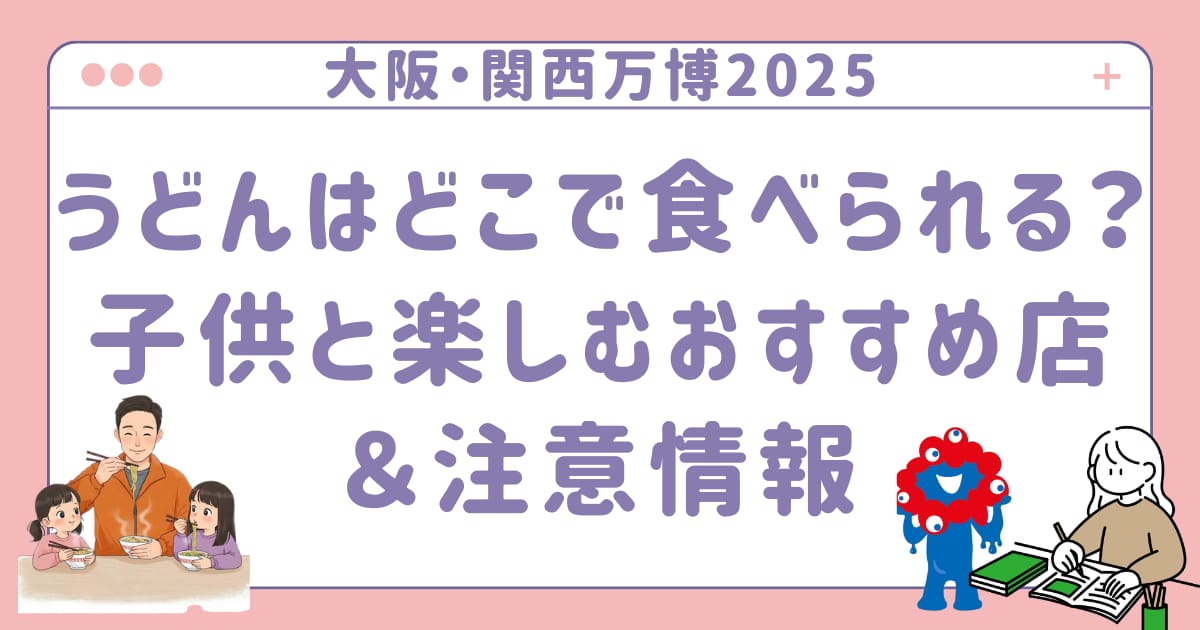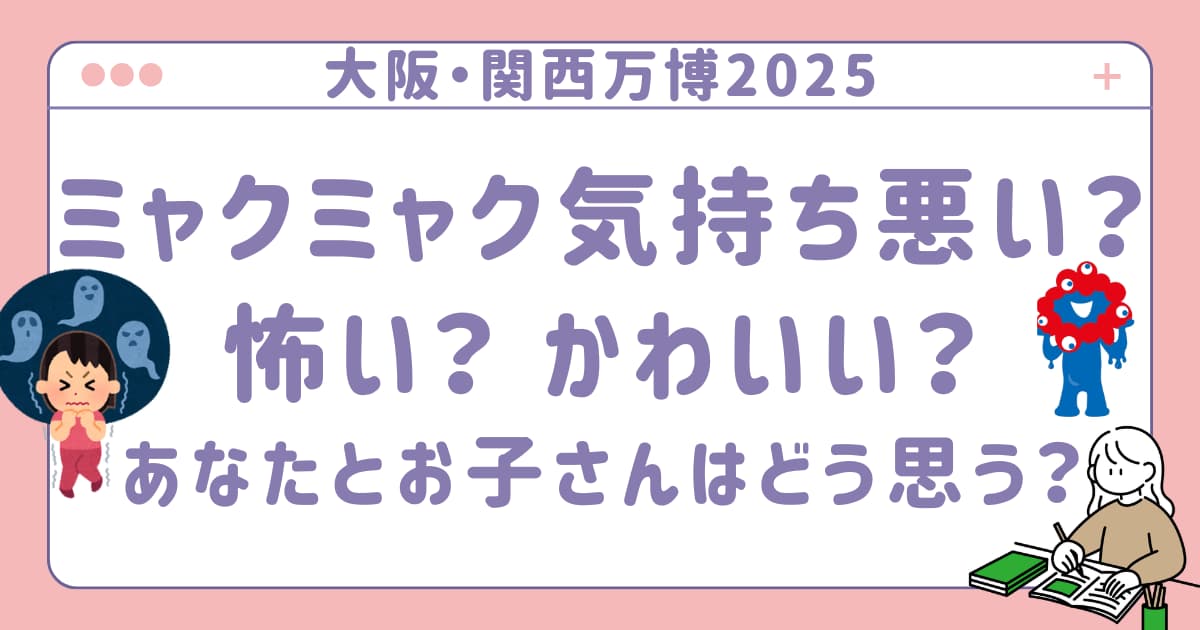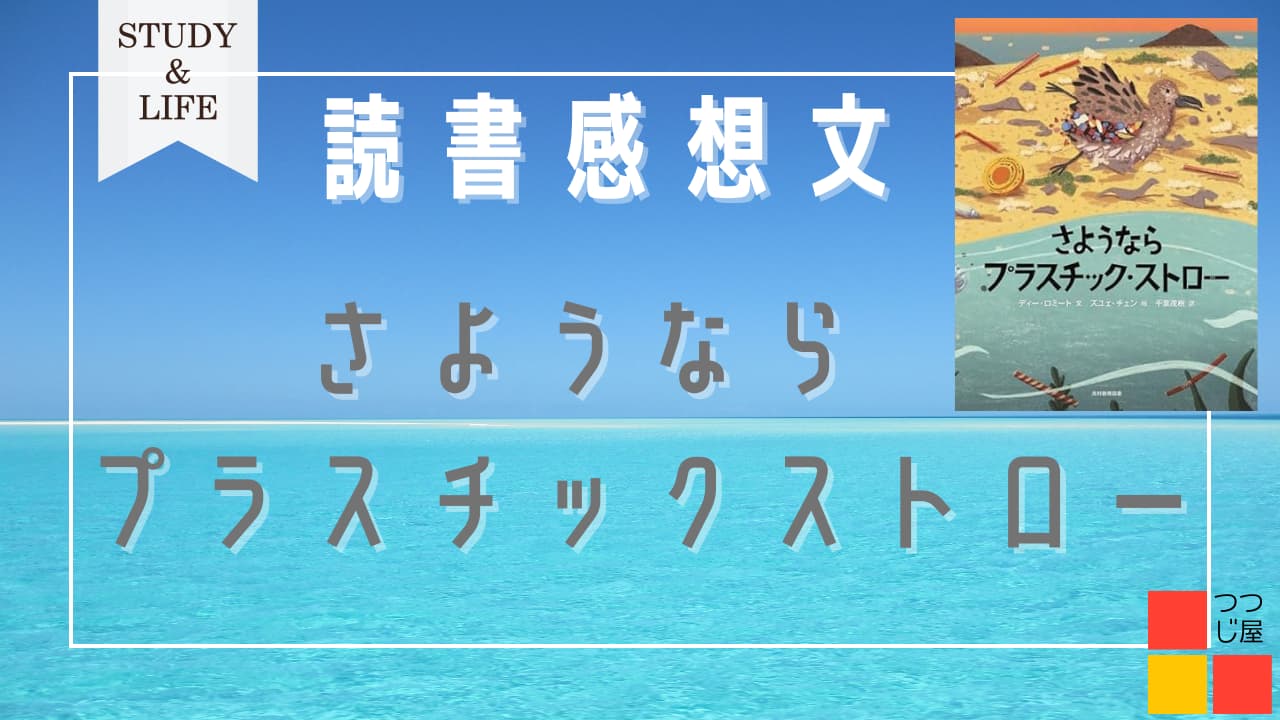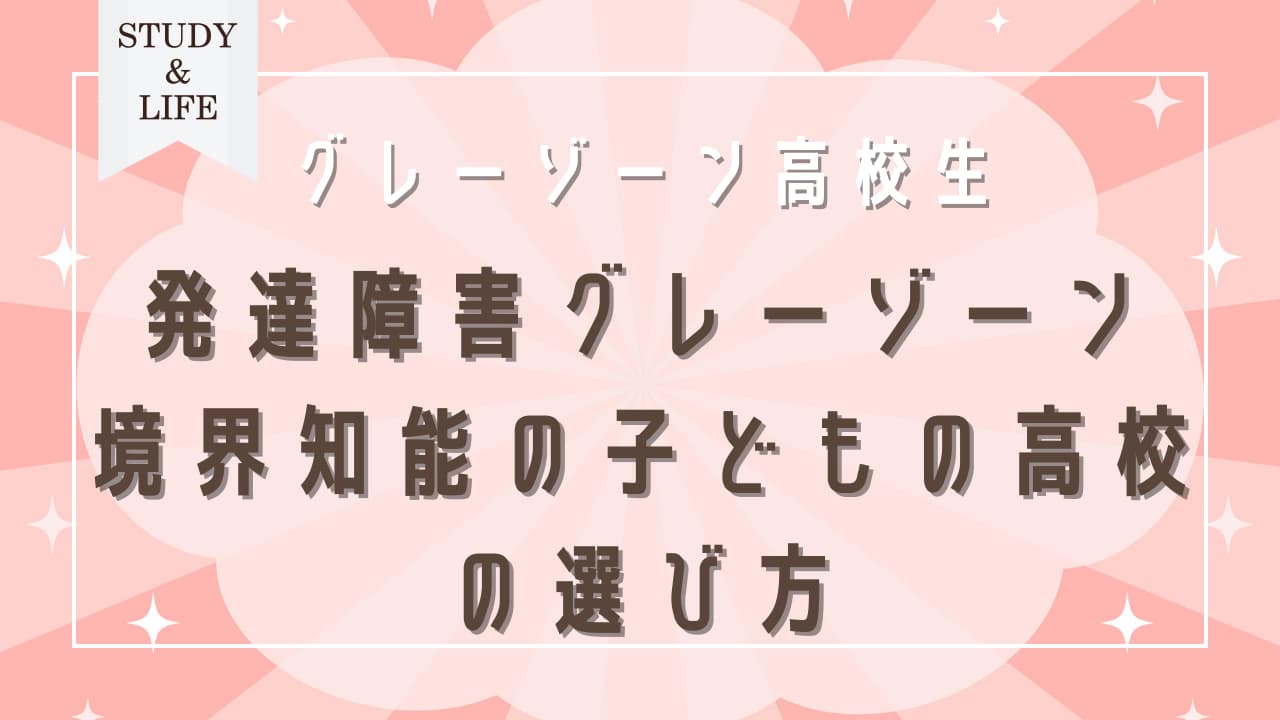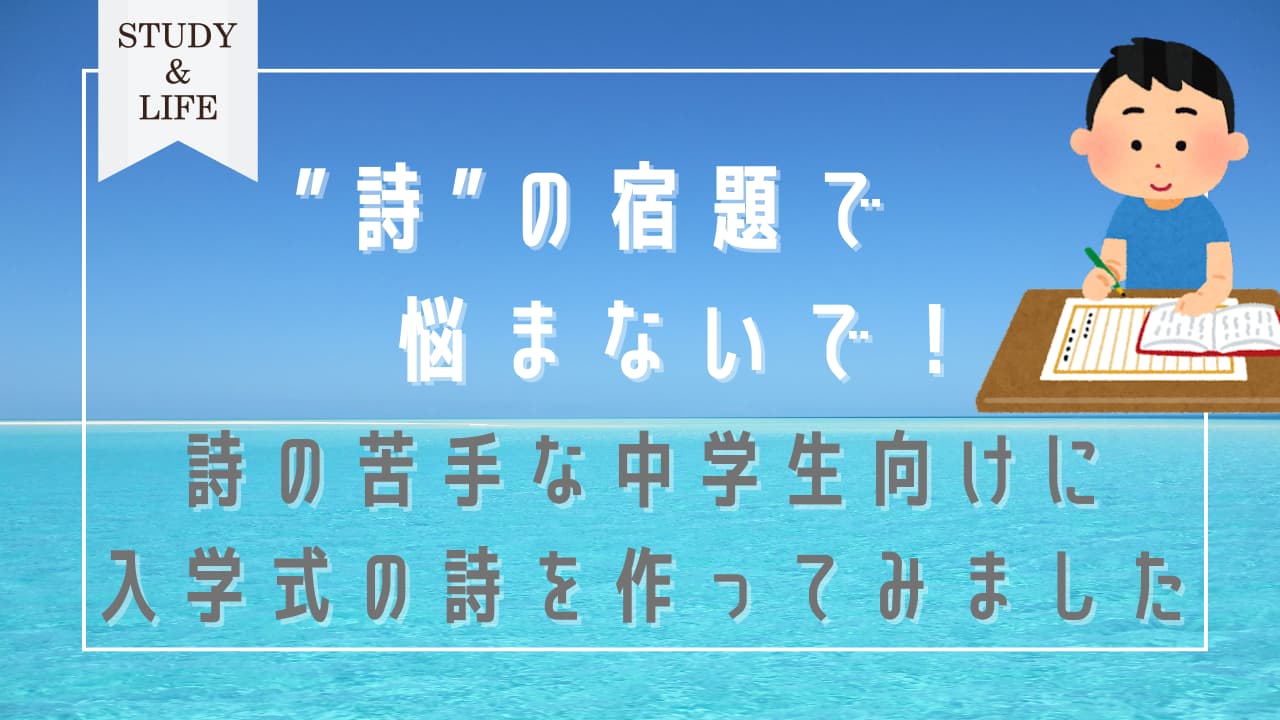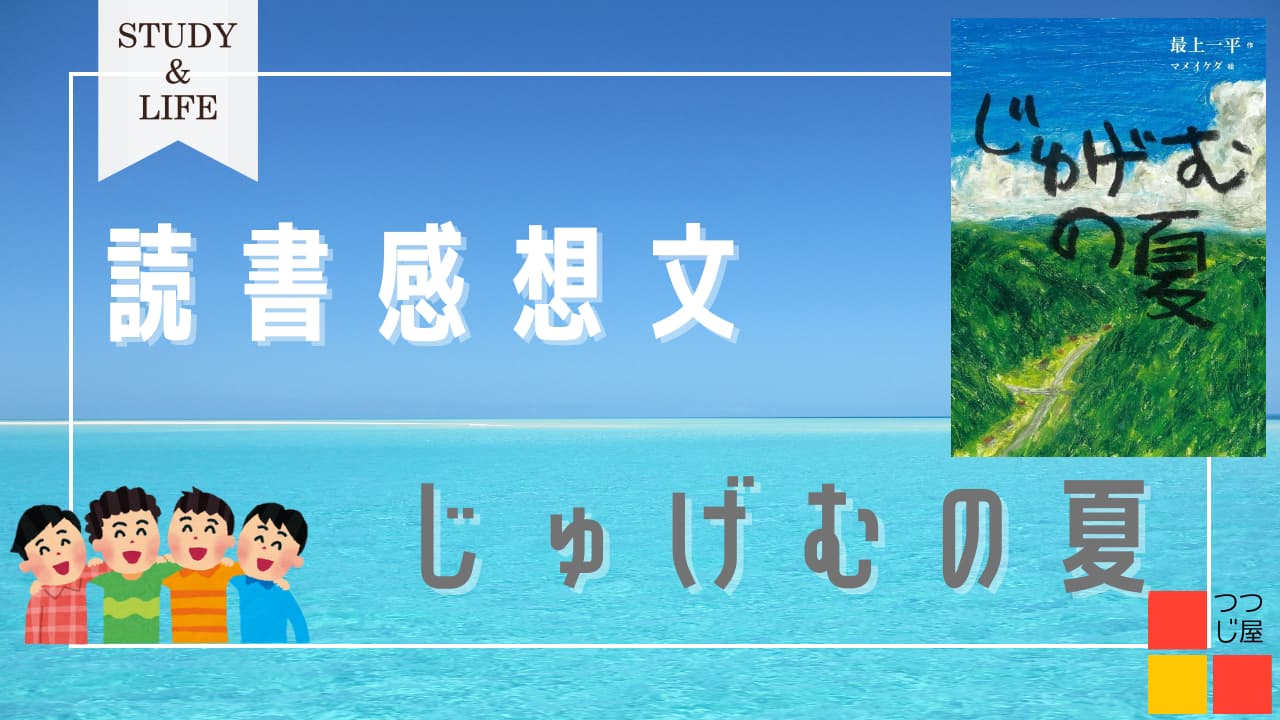発達障害グレーゾーンの特性を持っていたり、境界知能に当たるお子さんにとって、高校進学などの進路について悩むことが多いです。
勉強はできるけど、発達障害の特性が強く出ているので高校でうまくやっていけるのか不安。そもそもIQが少し低いので、勉強そのものが無理。人それぞれ気になるポイントも違います。
今回はわたしの住む地域の一般的な進学先のパターンをあげ、その違いや、そこへ行くためにはどうしたらいいのか、メリット・デメリットなどをお話しようと思います。
- ”発達障害”と”境界知能”は別物です。この記事は純粋に勉強ができない、能力的に困難のある境界知能の子どもの高校選びについて考えています。
- うちの三男は、田中ビネー式ではIQ80、WISCではIQ76の境界知能の持ち主で、高等専修学校に通っています。
- 境界知能の子どもの主な5つの進学先
①県立・市立などの公立高校 ②私立高校 ③高等専修学校 ④通信制高校 ⑤特別支援学校
うちの三男グレーゾーンボーイです。
私は地方在住の50代。子どもの教育に関わる仕事を週2回ペースでしている”つつじ屋”といいます。
家族:だんな 定年間近の会社員
長男 大学生 勉強が大好き
次男 大学生 自由が大好き
三男 高校生 ウルトラマン大好き
三男は発達障害グレーゾーンで境界知能の持ち主です。
このブログでは、この三男にまつわるエピソードや困り事などを、グチ多めでつづっていきたいと思っています。よろしくお願いします。
↓こちらは発達障害の子供と楽しみたい大阪万博の記事です↓
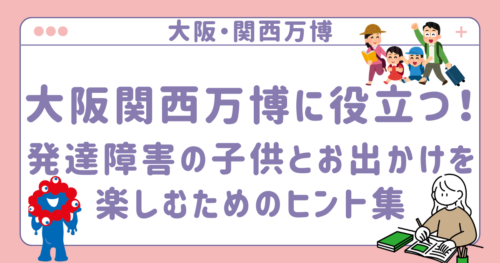
↓こちらは高校進学に向けて、普通級と支援級のどちらが良いかを考えてみた記事です。
境界知能の子どもの高校の選び方
- 今回考えるのは境界知能の子どもを想定
- グレーゾーンボーイの三男、高等専修学校に通っています
- 高校でIQのグレーゾーンはいくつですか?
- 境界知能の人は何が難しくなるのでしょうか?
今回考えるのは境界知能の子どもを想定
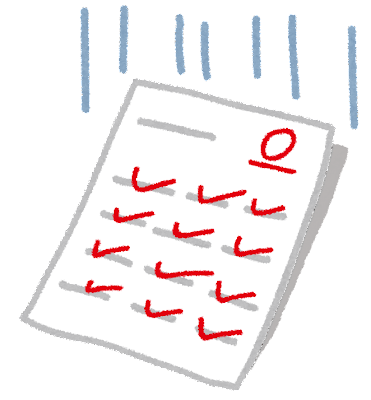
ここで一つお話しておきたいのが、今回のお話での高校の選び方は、”境界知能の子ども”を想定しています。
境界知能はIQで分けられます。
境界知能と言われるIQは70~85。
IQ50~70は軽度知的障害となります。
IQの基準値は100です。多くの人が90~110位です。境界知能に当たるのは、障害としては認定されないのですが、通常より生きづらさを感じやすいラインです。
一方の発達障害は、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)、チック症などああります。それぞれ特徴的な症状を持っています。
発達障害を持っていても、IQは高い人はたくさんいます。学校の勉強はよくできるけど、人付き合いが苦手とか。そういった生徒さんは、生きづらさはあるものの、内申点もあることが多く、テストもできたりするので、高校を選ぶ選択肢は若干広いかと思います。
そこで今回は、本当に純粋に勉強ができない、元々の能力的に困難のある境界知能の子どもが高校を選ぶときのパターンを考えています。
うちの三男のように、発達障害もグレーゾーンだし、境界知能の持ち主でもあって、どこからも支援を受けられない子どもを想定しています。
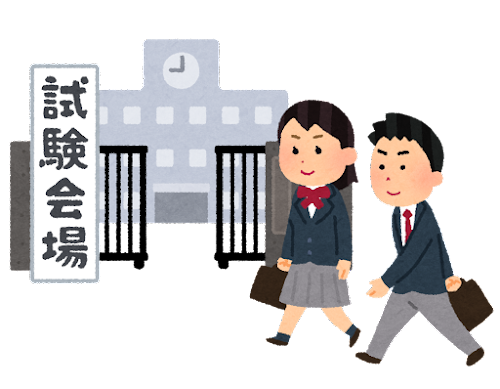
↓こちらは療育手帳の取得を申請しても、交付を受けることが叶わなかった時のお話です。
↓義務教育の終わりが見えはじめ、将来について考えてたころのお話です
↓こちらでは、特別支援学校へ入れないか試行錯誤していたころのお話をしています。
グレーゾーンボーイの三男、高等専修学校に通っています
うちの三男は発達障害グレーゾーン、田中ビネー式ではIQ80、WISCではIQ76の境界知能の持ち主です。(実感としてはそんなにIQがあるようには思えませんが・・・)
1歳半健診で落ち着きのなさと言語の遅れを指摘され、2歳半頃に広汎性発達障害という診断を受けています。それ以来ずっと児童精神科に通っています。
その三男、今は高等専修学校に通っています。本当は、彼の能力的には特別支援学校が一番合っていたと思います。けれど、療育手帳も精神の手帳も取得できないので、支援学校には行けませんでした。
今通っている高等専修学校は、当然三男にとっては勉強も難しく、受けたくもない(受かるはずのない)検定も強制的に受検させられます。おまけに三男の特性や境界知能であることについてのフォローや配慮は一切ありません。
少しでも三男にとって良いと思われる高校へ進学できるようにと、それこそ小学校の頃から考えてきました。しかし結果として、今の状況が正解だったとは胸を張っては言えない現実があります。
言えることは、三男には選択の余地があまりありませんでした。”三男の学力で行けるところ”を選ぶしかなかったのです。
私のように早くからあれこれ考えてもうまくいかないこともあります。もしかしたら勢いで”えいっ”と決めても案外結果オーライかもしれません。何がベストかはその時その時です。それでもあらゆる可能性を考えて、早めに動くことはマイナスにはならないと思います。
そのようのことを踏まえ、ここからは私の住む地域での一般的な高校進学のパターンをあげ、そこへ行くためにはどうしたらいいのか、メリットデメリットなども考えていこうと思います。

↓こちらでは、高校(専修学校)入学までの紆余曲折についてお話しています。
高校でIQのグレーゾーンはいくつですか?
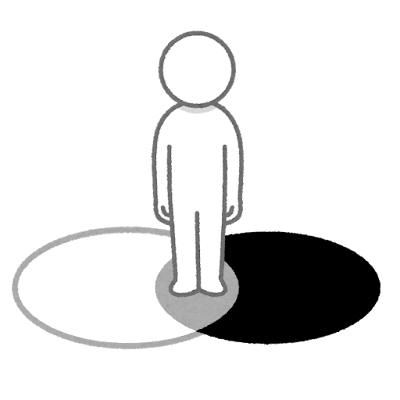
高校生におけるIQのグレーゾーン、いわゆる境界知能は、一般的にIQ70から85の範囲を指します。この範囲は、知的障害(IQ70未満)と平均的な知能(IQ90〜110)の間に位置しています。
境界知能の高校生は、学習面や社会適応面で困難を感じることがありますが、知的障害の診断基準には該当しません。そのため、必要な支援を受けにくい「グレーゾーン」と呼ばれることもあります。
日本の人口の約14%、およそ1700万人がこの範囲に該当すると言われています。高校生活では、学習の遅れや対人関係の難しさを感じる可能性がありますが、個々の特性や強みを活かした適切なサポートがあれば、充実した高校生活を送ることができますよ。
境界知能の人は何が難しくなるのでしょうか?

境界知能(IQ70-85程度)の方は、日常生活の中で以下のような課題に直面することが多いといわれます。
まず、抽象的な考え方や複雑な情報の処理が苦手(うちの三男もそうです)な傾向があります。例えば、暗黙のルールの理解や、複数の指示を同時に処理することが難しく感じられます。
学校や職場では、新しい知識やスキルの習得にやや時間がかかることがあります。特に、数的処理や読解力を必要とする課題では、より多くの練習や支援が必要となります。
社会生活においては、人間関係の機微を読み取ることや、状況に応じた適切な判断を下すことに苦労する場合があります。また、金銭管理や契約内容の理解など、生活に必要な実務的なスキルにも困難を感じることも多いです。
以上のような課題もありますが、適切なサポートや工夫によって少しでも克服できればと考えています。
境界知能にいつ気づきますか?

境界知能(境界線級知能)とは、IQ70~85程度の知的能力を指します。通常の知能(IQ85~115)よりもやや低いものの、知的障害(IQ70未満)には該当しない、なので「グレーゾーン」といわれるの状態です。
うちの三男の境界知能に気づくタイミングは、乳幼児健診の頃からで小学生の低学年からは段々とはっきりしてきました。
具体的には以下のような感じです。
・小学校入学後、学習内容が徐々に難しくなる中で、授業についていけない様子が目立ち始める
・指示を何度も繰り返さないと理解できない
・抽象的な概念の理解が難しい
・日常生活では大きな問題がないように見えるが、複雑な社会的状況での対応に苦手さがある
早期発見のためには、乳幼児健診や就学時健診での様子、保育所・幼稚園での集団活動の様子などが重要な手がかりとなります。
なかなか難しいですが、適切な支援があれば、その子の持つ能力(あくまでもその子の能力)を最大限に伸ばすことができるのではないでしょうか。
↓1歳半検診で「発達の遅れ」が見つかりました↓
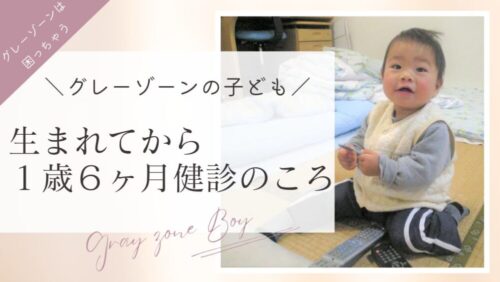
境界知能の子どもの主な5つの進学先
- 県立・市立などの公立高校
- 私立高校
- 高等専修学校
- 通信制高校
- 特別支援学校
進学先としては主に5つ。県立・市立などの公立高校、私立高校、高等専修学校、通信制高校、特別支援学校、です。では具体的にみていきましょう。
①県立・市立などの公立高校
公立高校とは
公立高校は、地域に密着した教育環境を提供し、一般的な教育を行っています。
進学条件は都道府県ごとに異なり、内申点や成績が重視されることが多いのが特徴です。公立高校のサポート体制は、私立高校と比べて少し劣る傾向があります。また地域の特性に応じた教育が行われるため、比較的地域社会との連携が強いのが特徴です。
私の地域の公立高校の特色
私の住む地方都市の地域で進学校と言われるのは、ほぼすべてこの公立高校です。偏差値の高い大学を目指す生徒さんは、ほとんどが公立高校へ進学します。
入学するためには内申点、当日試験の点数、共にかなりの高得点が必要です。推薦もありますが、極めて少数で難関です。
公立高校は2校受験できます。自分の目指す学校と、少し余裕のある学校の2校を受けるわけです。多くの場合、さらなるすべり止めとして、私立高校も受験します。
当然それぞれに受験料はかかりますが、私立に合格した場合、入学金を納めなければなりません。納めないと合格取り消しになるので、捨てる覚悟で納めるわけです。まあ、第一志望が公立なら、捨てることになっても喜ばないとですが・・・。
どちみち、内申点が11~13点ほどの三男にはおよびでない・・・。
公立高校の中でもレベルがあって、授業の難易度も違います。教科書の内容が違うのです。トップ校は入学と同時にトップスピード、MAX量での学習が始まります。ギリギリ入学できたレベルの生徒さんには、かなりキツイ状況になることもあります。
それでも、学力の高い生徒さんと刺激しあい、さらに自分を延ばすことも可能です。トップ校の常識はトップ校に入らないと分からないものです。その常識の中にいると自然とレベルアップする、ということもあります。
公立高校のメリット(私の地域)
メリットは、大学進学を考えた時、選択の幅がとても広がる、ということです。
難関と言われる大学を目指すこともできます。そもそもそこにいる生徒さんの偏差値は高いので、その学校ではさえない成績だったとしても、実際の学力は結構ついているということもあります。
公立高校のデメリット(私の地域)
デメリットは、まず入学するのが難しい。
学習内容も高度で、学習量も多く必要です。ついていくのはかなり大変。就職する生徒さんは普通科にはまずいないので、就職を希望すると自分でかなり動く必要があります。就職に関しての情報はほとんどないと言えます。
また、入試の時は内申点が必要です。

公立高校卒業後の進路
公立高校の卒業生の約50%が大学に進学します。
沖縄では約50%、日本全体では56.6%の進学率を誇り、多くの生徒が高等教育を目指しています。公立高校は、地域に密着した教育を提供し、大学進学を視野に入れたカリキュラムも多く組まれています。
公立高校と私立高校の平均的な学費の違い
| 学年別学費 | 公立高校 | 私立高校 |
|---|---|---|
| 1年生 | 51万円 | 116万円 |
| 2年生 | 46万円 | 90万円 |
| 3年生 | 40万円 | 85万円 |
| 3年間合計 | 137万円 | 291万円 |
②私立高校
私立高校とは
私立高校は、独自のカリキュラムや教育方針を持ち、個別のサポートが充実していることが多いのが特徴です。
推薦入学の条件には、第一志望であることが求められます。私立高校は、比較的面倒見が良く、個別のサポートが手厚いため、生徒一人ひとりの特性に応じた教育が可能と云われています。
私の地域の公立高校の特色
全国的にみると、私立高校の超トップレベル進学校というのは多数あります。しかし私の住む地域では、学力レベルとしては公立高校よりも低くなります。
中学校での内申点があまりない(30点ないくらい)、テストの実力としても不安がある、という生徒さんや、「この高校で○○がやりたい!」という明確な希望をもった生徒さんが受験します。
私立でも一般入試と推薦入試があります。この地域では推薦で受ける生徒さんが多数です。ある学校では推薦での合格者が全体の80%にもなります。残りの20%の枠を一般入試受験者や公立高校との併願受験者が狙うことになります。
推薦入試はその学校1校のみしか受験できません。そして、推薦入試を受けるためには中学校校長からの推薦が必要になります。基準となる内申点を満たしているか、学校生活の様子、部活動の様子などから、校長を含めた中学の先生方が会議をし、その生徒を推薦できるかを決めます。とはいえ、特別に秀でた表彰だったり、活動が必要なわけではありません。真面目に授業を受けているか、人間関係は良好か、その辺りが重要です。
仮に推薦入試で不合格でも、その後の一般入試に出願することができます。とはいえ、私立推薦はまず落ちないと言われております。
私立高校のメリット(私の地域)
メリットは、様々な特色を持った学校があり、自分に合った学校を選びやすい、ということです。
運動系に力を入れている学校、女子高で生活単元系のコースのある学校、中等部もあるマンモス校で、特進科で大学受験を目指すコースのある学校、などなど。いろんな希望を持った生徒さんをバックアップしてくれます。
大学進学、就職どちらの道も選べ、サポートもあります。
また、どちらかと言えば、公立よりも自由なイメージがあります。キラキラしたイメージもあります(私の勝手な思い込み?・・・)。
私立高校のデメリット(私の地域)
デメリットは、トップレベルの大学を目指そうとすると、かなりの努力が必要になることです。
トップの公立高校とはカリキュラムの違いもあり、どうしても力の差が生まれます。
そして受験するためには内申点が必要です。
また、無償化とは言えその恩恵を受けられない家庭では、高額の学費もかかります。
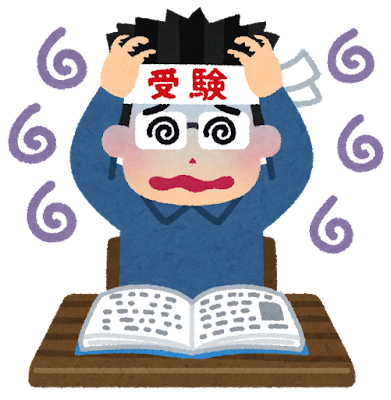
私立高校卒業後の進路
私立高校の卒業生は、大学や専門学校への進学が一般的です。
面倒見が良く、個別のサポートが充実しているため、生徒一人ひとりの特性に応じた進路選択が可能な場合が多く、希望にそうような道へ進む事がきっとできるでしょう。
③高等専修学校
高等専修学校とは
高等専修学校は、専門的な技術や知識を学びながら高卒資格を取得できる教育機関です。
卒業後は、大学や専門課程への進学も可能で、実践的なスキルを身につけることもできます。専門的で仕事に役立つような教育を受けているので、就職などにも有効です。
私の三男が通う高等専修学校
こちらの高等専修学校がうちの三男が通っている学校です。
”専門学校”というのはよく聞くと思いますが、”高等専修学校”は聞きなれない方も多いのではないでしょうか。
平たく言えば専門学校の高等部。専門学校は高校を卒業した人が行くところで、高等専修学校は中学を卒業した人を対象としています。
もともと専門学校なので、専門科目を多く学びます。学校によって情報系、電気系、調理系、家政系など、主に学ぶ科目が変わります。また、専門学校系の学校ならではですが、検定取得に力を入れている学校も多いです。
高等課程ということで、通信で技能連携校の授業を受け、高校卒業の資格もきちんと取れます。当然、技能連携校のスクーリング、レポート提出などもあります。また、卒業時には、もともとの専修学校と技能連携校の2校の卒業証書がもらえます。
入試は推薦入試、AO入試、一般入試など、学校によって多少異なります。
三男の学校の場合、一般入試は数学と国語の学科試験と面接。AO入試は作文と面接。推薦入試は面接のみ。三男は内申11点でしたが、学校からの推薦を頂き、推薦入試を受けて合格しました。AO入試でもよかったのですが、作文は無理だったのと、かろうじて内申点がついていたので、推薦入試にしました。
また、三男の学校のAO入試は、不登校だったり支援級在籍のため、内申点のない生徒さんのためのものでもありました。そう、支援級では内申点が付きません!なので、学校によっては支援級の生徒さんを受け入れてくれない所もあります。体験入学などで細かく聞いておきたいポイントですね。
ある高等専修学校の入試問題を見たことがありますが、小学校卒業くらいの難易度でした。だとしても、うちの三男には難しかったと思うので、推薦を頂けて有難かったです。
高等専修学校に推薦入試で受験した場合、不合格はまずないようです。ある意味、三男のような境界知能の持ち主で、普通の高校からはあぶれてしまう生徒の受け皿の役割もしてくれています。三男の学校は支援級在籍だった生徒さんも受け入れていますし、不登校の生徒さんも受け入れています。
専修学校のメリット
メリットは、専門的な知識や技術を身に着けられることです。
もとは専門学校なので、「これが学びたい!」という明確な目標がある生徒さんならやりがいがあると思います。技能連携校があって、通信で学ぶことにより高校卒業の資格も取れます。
入試の形態も様々で、支援級に通っていて内申点がついていない生徒さんでも受け入れてくれる学校も多くあります。
専修学校のデメリット
デメリットは、やはり難関大学に進学したいとなると、履修していない科目が多いので、受験することができないということもあります。
授業の内容も易しいので、指定校推薦でもない限り、大学進学は難しいだろうなというのが正直なところです。
それなら就職はと言っても、幅広く選べる、とはいかないので、自分で動くことが多いです。高等専修学校への入学は比較的易しいですが、卒業後の進路は簡単ではないかもしれません。
学費は私立高校とほぼ同じです。ということはやはり、無償化といっても対象にならないご家庭もあるので、そうなると高額の学費がかかってきます。。
私立高校もそうですが、高等専修学校も学校によって雰囲気や先生方の考え方が大きく異なります。この辺りも体験入学でしっかり確かめたいポイントです。失礼なくらい質問していいと思います。

高等専修学校卒業後の進路
高等専修学校の卒業生は、専門学校や大学への進学が可能です。
専門的なスキルを学びながら高卒資格を取得できる教育機関であり、実践的なスキルを身につけることができます。この専門性により、就職やさらなる専門教育への道む事もできます。
ちなみに、うちの三男は就職予定です。
↓こちらでは、高校(専修学校)の入学費用についてお話しています。
④通信制高校
通信制高校とは
通信制高校は、自宅学習が中心で、柔軟な学習スケジュールを組むことができます。
毎日通学する必要がないため、個々のペースで学習を進めることが可能です。学費は私立で年間20〜60万円程度で、公立高校に比べて学費が高い傾向となっています。
この近頃大変注目されているのが通信制高校。その名の通り通信教育が基本です。学校によっては毎日通えたり、3日くらい通えたり、それぞれ自分でスケジュールを決められたり、学習のスタイルも幅広くなっています。
その多くが単位制です。一方、全日制高校は学年制。学年ごとに修了するべき内容が決まっていて、留年もあります。しかし単位制は卒業までに単位を取得すればいいので、基本的に留年はありません。
単位取得のためには課題レポートを提出し、スクーリングに出席し、単位認定試験に合格しなければなりません。
不登校だった生徒さんや発達障害を持つ生徒さん、様々なタイプの生徒さんを受け入れています。
入試というものはありますが、内申点を合否の判断基準とはしていないので、面接でごく普通の対応ができていればほぼ合格できます。支援級からの受け入れについては各学校で対応が違うので、しっかり確かめておきたいですね。
通信制高校のメリット
メリットは、通学することが絶対ではないこと。
通学パターンを選べ、卒業までに必要な単位を取得すればいいので、留年ということがありません。毎日通うのがつらい、というお子さんでも、自分のペースで学びやすいです。
また、受験時に内申点はいらないので、様々な事情を持った生徒さんが受験できます。
そして、通信制高校でも高校卒業の資格が取れます。
通信制高校のデメリット
デメリットは、やはり学費が高額であること。
支援金はありますが、対象でなければ高額の学費を納めることになります。
また、学校によってカラーがかなり違うので、入学後に戸惑うことがあるかもしれません。通信制とは言っても、入学前に実際に何度か訪問しておくことをお勧めします。
学校の規模、学習内容、登校パターン、学費など取りこぼしなく調べて、一番合った学校を見つけましょう。

↓お友達が専修学校を辞めて、通信制高校へ転入学しました↓
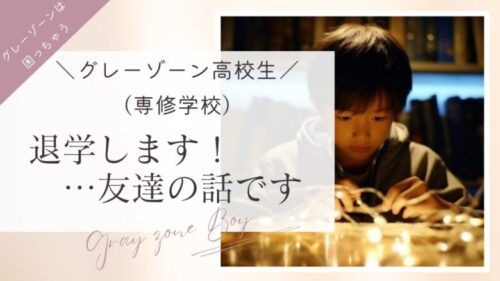
「不登校専門オンライン個別指導ティントル」もおすすめします!
「不登校専門オンライン個別指導ティントル」
通信制の教育受講の一つとして『ティントル』があります。
世の中に、不登校支援をする団体は多くあります。
しかし、学校と同じような通いを絡めたサポート施設ばかりであったりします。
逆に、オンラインフリースクールになると映像授業のみで、個別指導がないなど不登校生の学習をサポートするものとしては不十分なものも多いと感じます。
そういった声から生まれた、新しいカタチとして活動しているのが、オンライン専門の不登校サポート事業『ティントル』になります。
詳細は、以下のリンクから確認できますので、よろしければ見て行ってくださいね!
↓「不登校専門オンライン個別指導ティントル」↓
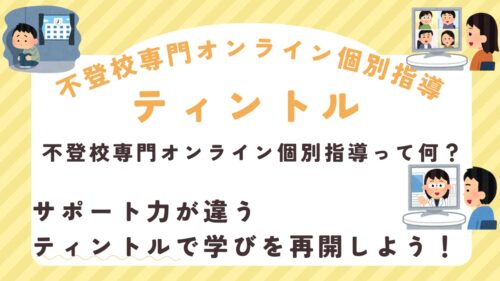
⑤特別支援学校
特別支援学校とは
特別支援学校は、発達障害や境界知能の生徒に特化した教育を提供しています。
発達障害と知的障害を併存している場合に入学が可能で、個々の特性に応じた支援が行われます。高等部では高卒資格は得られません。
そしてこちらは基本的に身体・精神・療育などの手帳を所持している生徒さんを対象とした学校です。
特別支援学校には小学部や中学部もありますが、小・中学校は地域の学校の支援級に在籍し、高校から支援学校へ通う生徒さんも多いです。
気をつけたいのが、中学校で支援級にいたからといって、特別支援学校に行けるわけではない、ということです。
中学校の普通級では勉強が難しすぎるから、落ち着きがなさすぎるから、といった「普通級では少し厳しいから」という理由で支援級に在籍することもあると思います。なぜなら、普通級か支援級かを決めるのは保護者だから。普通級に在籍していて、あまりにも勉強ができない場合などでも、学校側から支援級への転籍を勧められることはありません。大変でも、保護者が普通級で過ごさせようと思えば、保護者の意向が尊重されます。
しかし、いざ高校受験という場面で悩むことがあります。特別支援学校に行くためには何らかの手帳が必須です。しかし、そういった微妙なレベルの生徒さんの場合、療育手帳などは持っていないことが多いです。そのため、特別支援学校には行けないことが多いです。逆に普通科の高校に行きたいと思っても、内申点がないのでその道はとても険しい、というかほぼ不可能になってしまいます。
障害や手帳を持っていなくても中学校の支援級に在籍することはできますが、高校進学を考えた時、難しい選択を迫られることがあることを胸に留めておくべきですね。
三男も能力的には特別支援学校が適していると思っているので、中学3年生の時に2つの特別支援学校で面談をしていただきました。そのどちらでも言われたのが「やっぱり手帳が必要」ということです。仮に入学できたとしても、在校中に何らかの手帳を取得する必要がある、ということでした。病院の先生にも相談しましたが、三男が手帳を取得できる見込みはなく、支援学校をあきらめた、という経緯があります。
手帳を所持し、障害者枠で就職できたら少しは生きやすいのでは、と考えていたのですが、その道はなくなりました。
支援学校にも入試があります。特に人気のある”産業科”などと言われるコースです。大手企業の障害者枠での就職を目指す、いわばエリートコース。こちらは定員も少なく、不合格となる生徒さんも結構いるそうです。なので、滑り止めとして、産業科ではなく同じ学校の普通科も受験するそうです。(支援学校の先生談)
学費についてはその支援学校が県立や私立なら公立高校とほぼ同じです。経済的な負担は割と少なくすみそうです。
高校卒業資格はとれません
補足ですが、特別支援学校を卒業しても、高校卒業の資格はとれません。
仮に手帳なしで特別支援学校に入学しても、学校に来る求人は障害者枠でのものがほとんどです。なので、一般の求人票から探して就職先を見つける必要が出てきます。その時、”中卒”という扱いになります。就職活動するうえで、どうしてもハンデになります。もっと言えば、支援学校卒業後に高卒認定試験を受けて合格したとしても、高校卒業の資格ではないので、やはり”中卒”のままです。この点も考慮に入れておきましょう。
特別支援学校のメリット
メリットは、手帳を所持しているお子さんそれぞれの特性をきちんと把握したうえで、学習のみならず、生活面の能力向上も目指してくれるところです。
一般企業の障害者枠での就職を目指すこともできます。学習面で苦しむことはまずないのではないでしょうか。
卒業後の進路も比較的手厚くサポートしてくれます。
受験時に内申点は必要ありません。
特別支援学校のデメリット
デメリットは、療育・精神・身体などの手帳がいること。
希望しても、手帳がなければ受験できません。「うちの子、勉強苦手だから。」では入学できないのです。
また、高校卒業の資格は取れません。

↓こちらでは、特別支援学校へ入れないか試行錯誤していたころのお話をしています↓
発達障害グレーゾーン・境界知能の子どもの高校の選び方 まとめ
以上、境界知能の子どもの5つの進学先を見てきました。
ひとつポイントとなるのが内申点。公立・私立高校については内申点が必ず必要です。内申点が合否判定の大きなポイントです。
しかし、中学校で支援級に在籍しているとこの内申点がつきません。「中学でずっと支援級だったけど、勉強はできるから公立高校受けてみたい。」と思っても、内申点がないので受験することはできなくなってしまいます。
なので、お子さんが発達障害グレーゾーンや境界知能で、中学校から普通級か支援級か迷っている場合、本当に慎重に考えた方がいいと思います。
そしてその選択って実は小学校から始まっています。お子さんに合ったペースでできるからと支援級に在籍していた場合、中学校でも支援級を選ぶことが多いです。支援級にいれば配慮もあるし、無理なく過ごすことができます。でも、内申点はつきません。そうなると、行きたい学校を受験できないかもしれません。
もちろん、無理してでも普通級に行った方がいい、とは全く思いません。ただ、そういう可能性があることだけは頭の隅に置いておいても損はないかと思います。
今は様々な事情を抱えるお子さんが自分の進路を考えるとき、わりと選択する幅があります。子どもの性格、学力、できること、やりたいことなども様々です。
三男は境界知能ゆえなのか何なのか、自分の進路や将来については何も考えていません。なので、進学先も中学校の先生と親で決めてしまいました。今三男は特に不満はなさそうです。「どこに行きたい」とか「何がやりたい」ということがない、というより、そういうことが「わからない」と言った方がよさそう。考えていないのではなく分からないのです。グレーゾーンや境界知能のお子さんをお持ちの場合、そんな見方もあるかもしれませんね。
そして言えるのは、とにかく早めに動くこと。たくさんの人に相談して、たくさんの学校を見ること。面倒でも、子どもが乗り気でなくても、是非実際に見て、聞いて、感じてみましょう。より良い道が見つかるヒントが得られますよ。

生まれてから~保育園までのできごと
↓こちらの記事は、生まれて間もないころのお話です。
↓三男が通っている、児童精神科の先生のお話
グレーゾーンの三男にはこんな「あるある」な特徴もありました。
保育園時代に気になっていたことの記事を書いてみました。よろしければお読み下さい。
【発達障害】グレーゾーンの子供のひどいいびきは、アデノイドによる睡眠時無呼吸症かも?治療で劇的改善!発達にも影響!?治療費は?
小学生時代
こちらは小学1年生、小学校でおもらしばかりしていた頃のお話です
小学1年生、勉強やおもらし、のどの手術(アデノイド除去)について書いてます
小学4年、普通級の子どもさんと上手くコミュニケーションが取れなかったお話です。
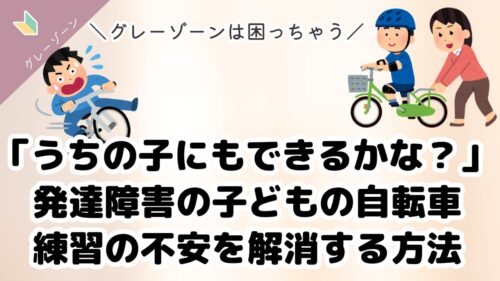
中学生時代
↓療育手帳の取得を申請しても、交付を受けることが叶わなかった時のお話
↓高校(専修学校)入学までの紆余曲折についてお話
↓義務教育の終わりが見えはじめ、将来について考えてたころのお話
↓三男の中学生時代について書いています。(現在、高校生です)
進路と将来
↓中学生になって支援級と普通級のどちらが良いかを考えてみた記事
↓体調の悪さを誰にも伝えられない不安について考えた記事
↓高校(専修学校)入学までの紆余曲折
↓こちらは日本政策金融公庫で借りた学費のお話です↓


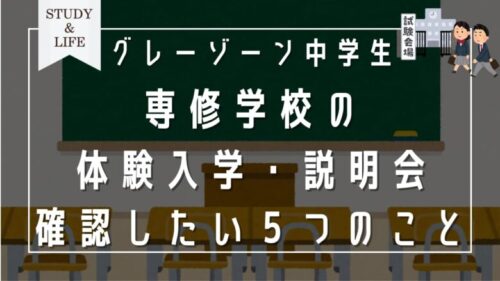
高校生時代
↓こちらは高校(専修学校)へ入学してから初めての中間テストの結果です。
↓こちらは”専修学校各種学校連合会”についての記事です
↓何もできなくてもいい、たまには外へ出てあそんでみよう!↓
↓こちらは発達障害の子供と楽しみたい大阪万博の記事です↓
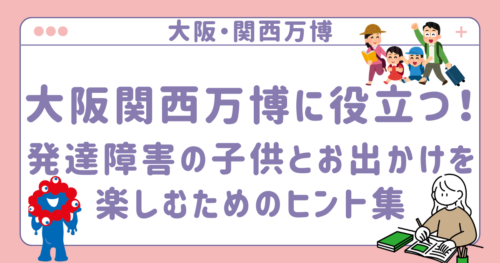
出典:文部科学省公式サイトより