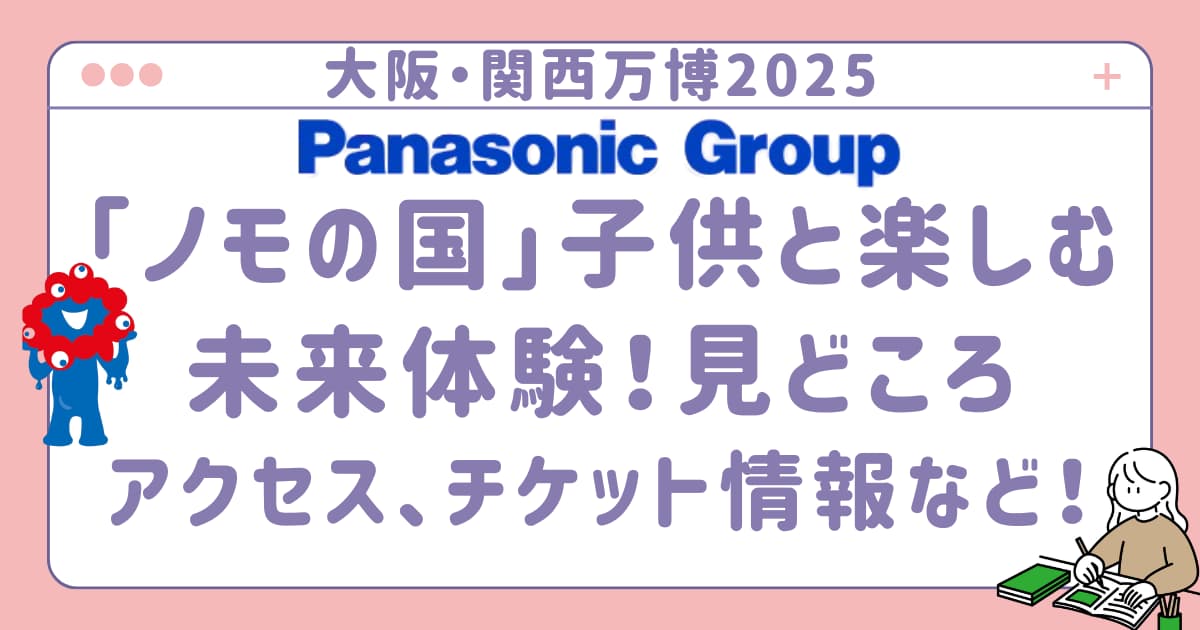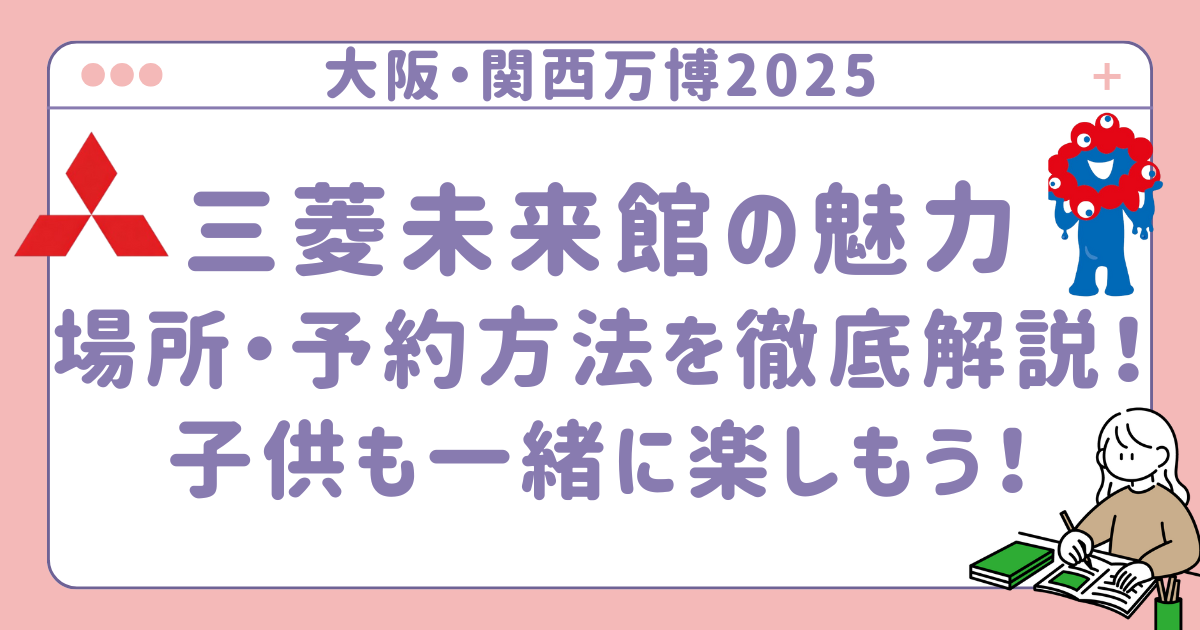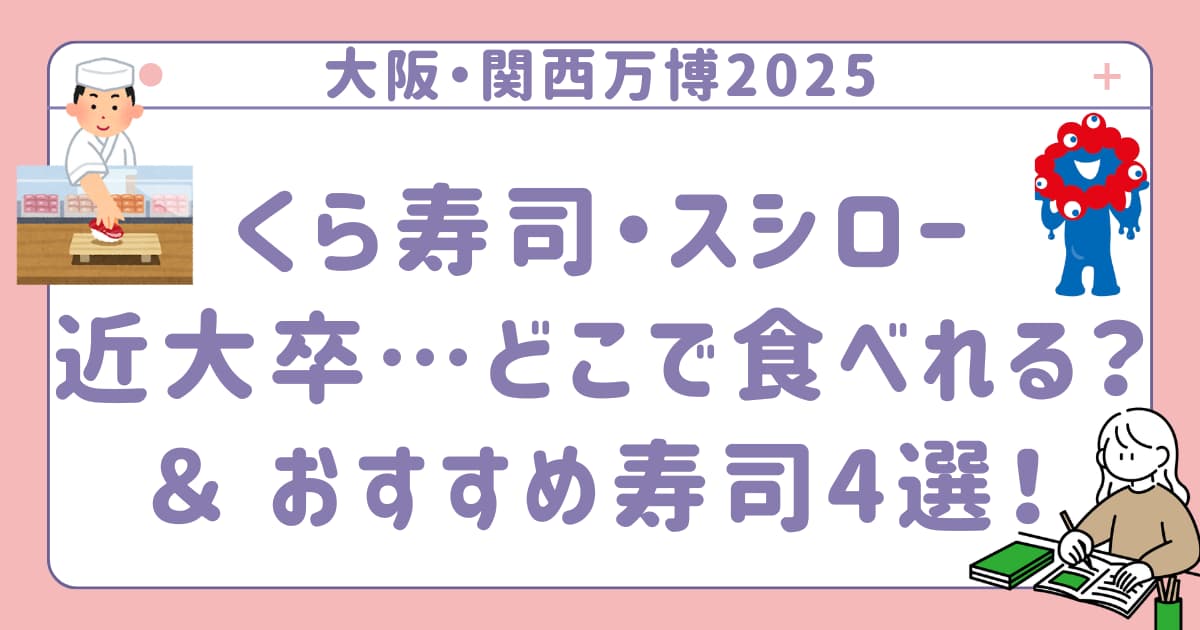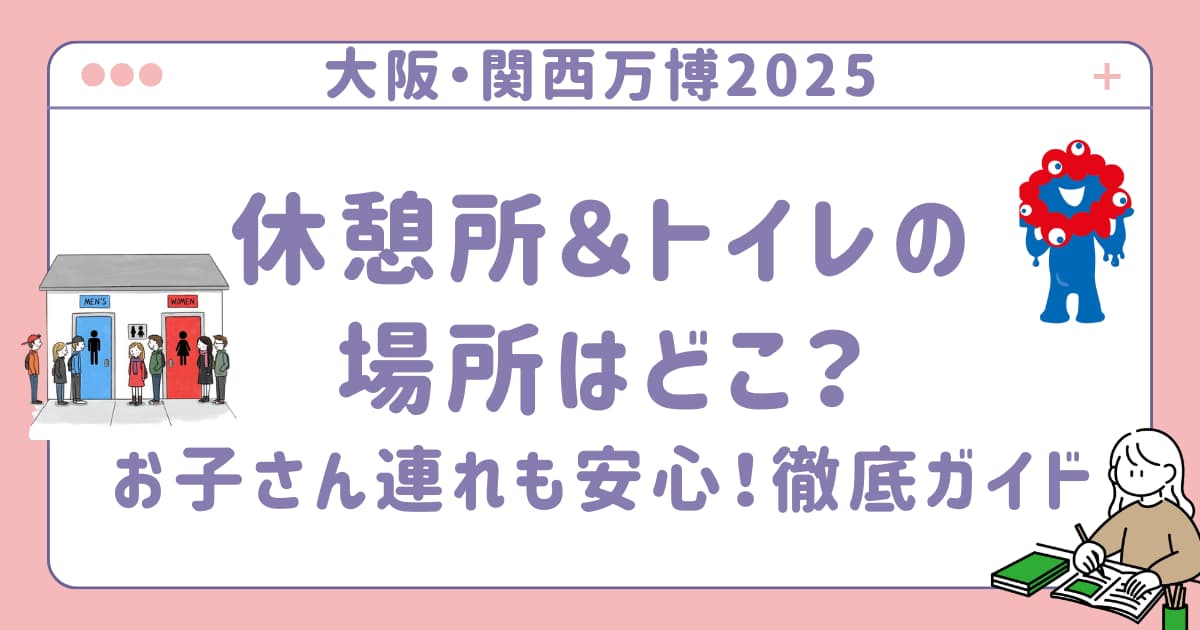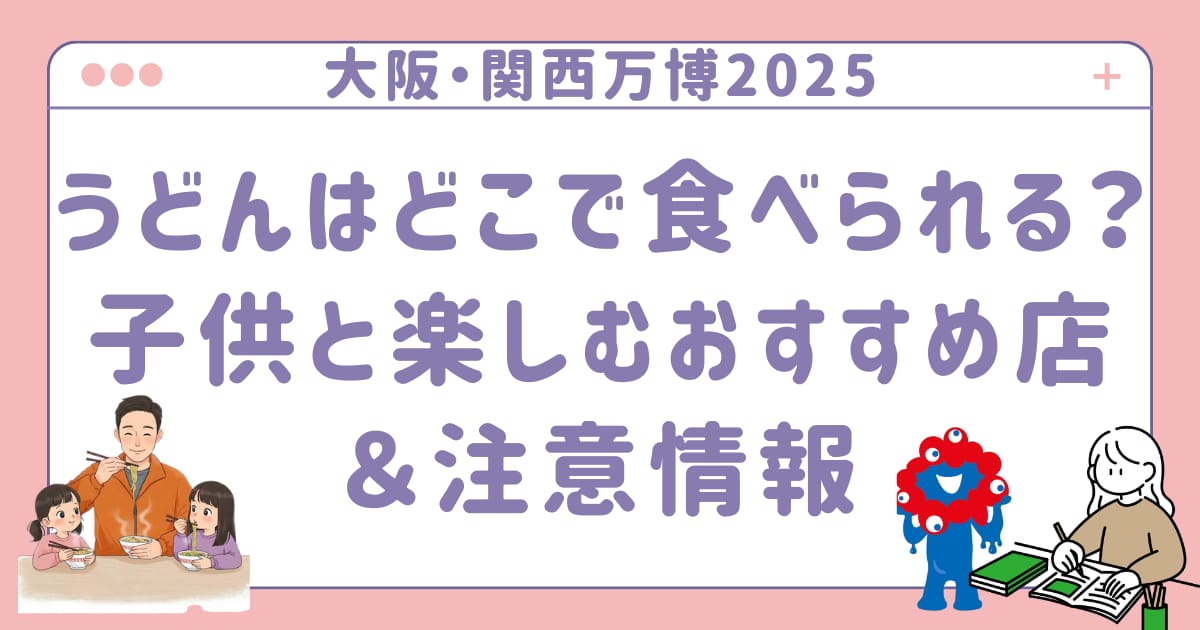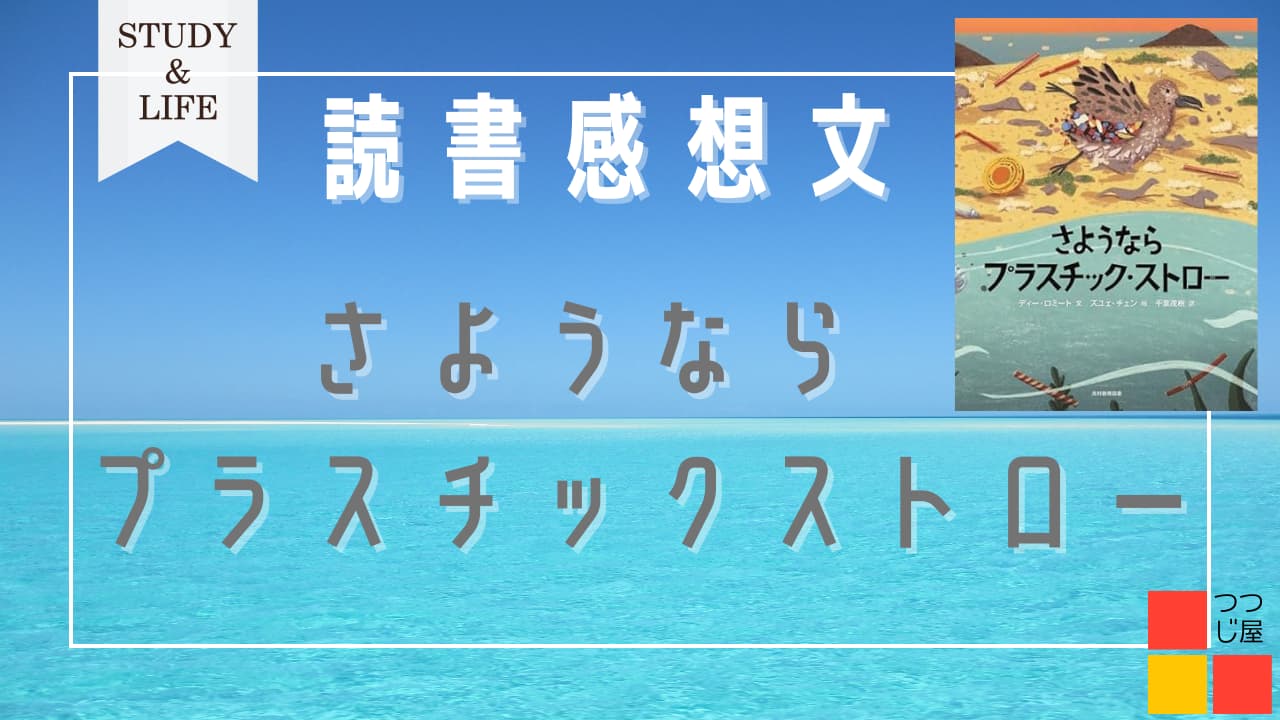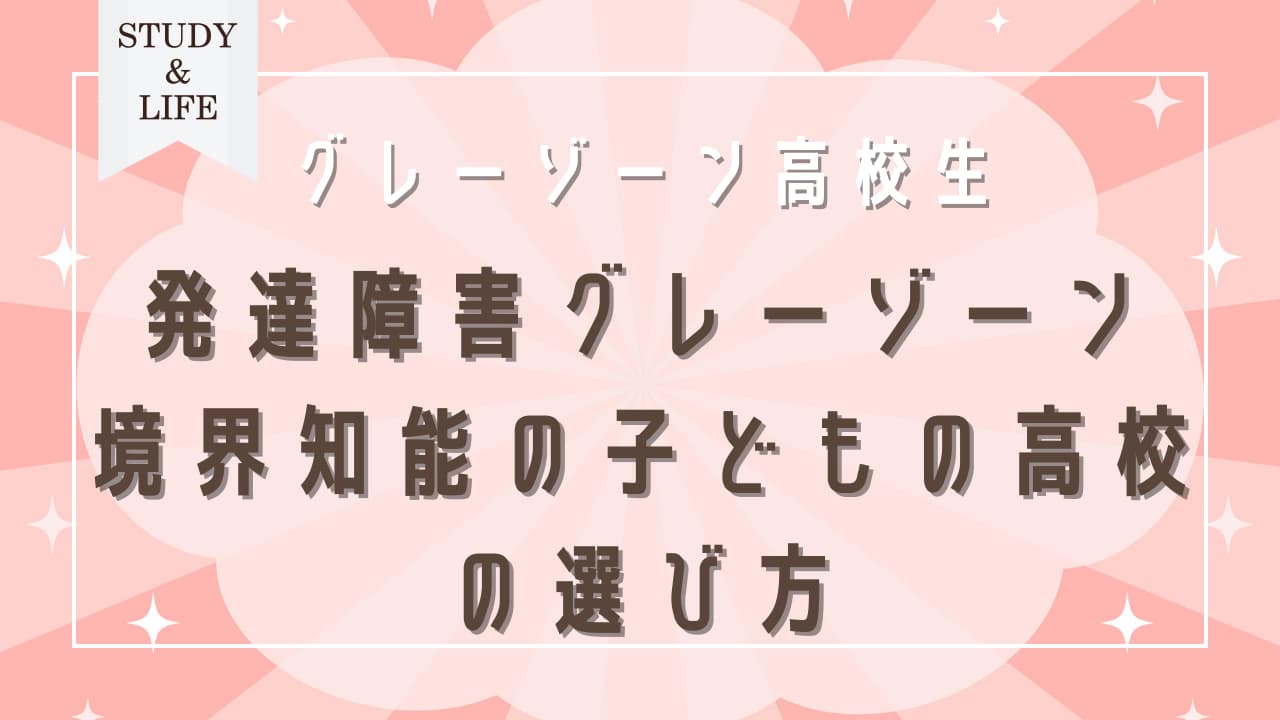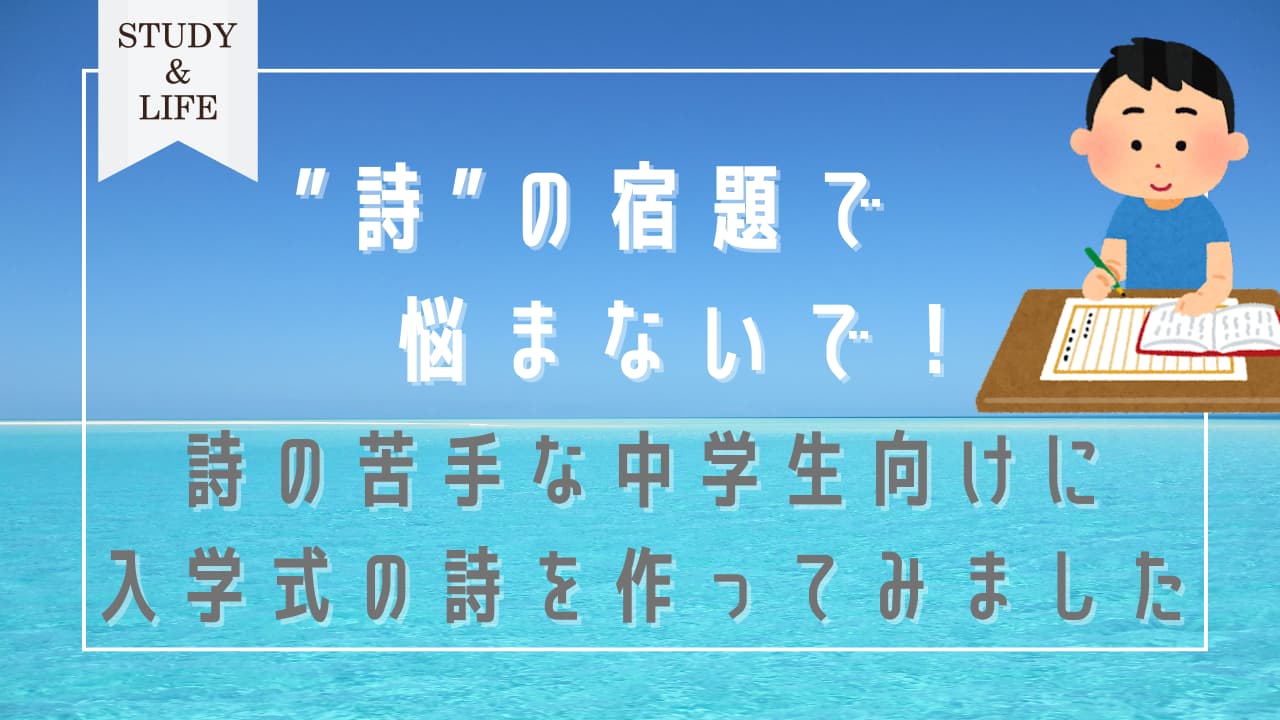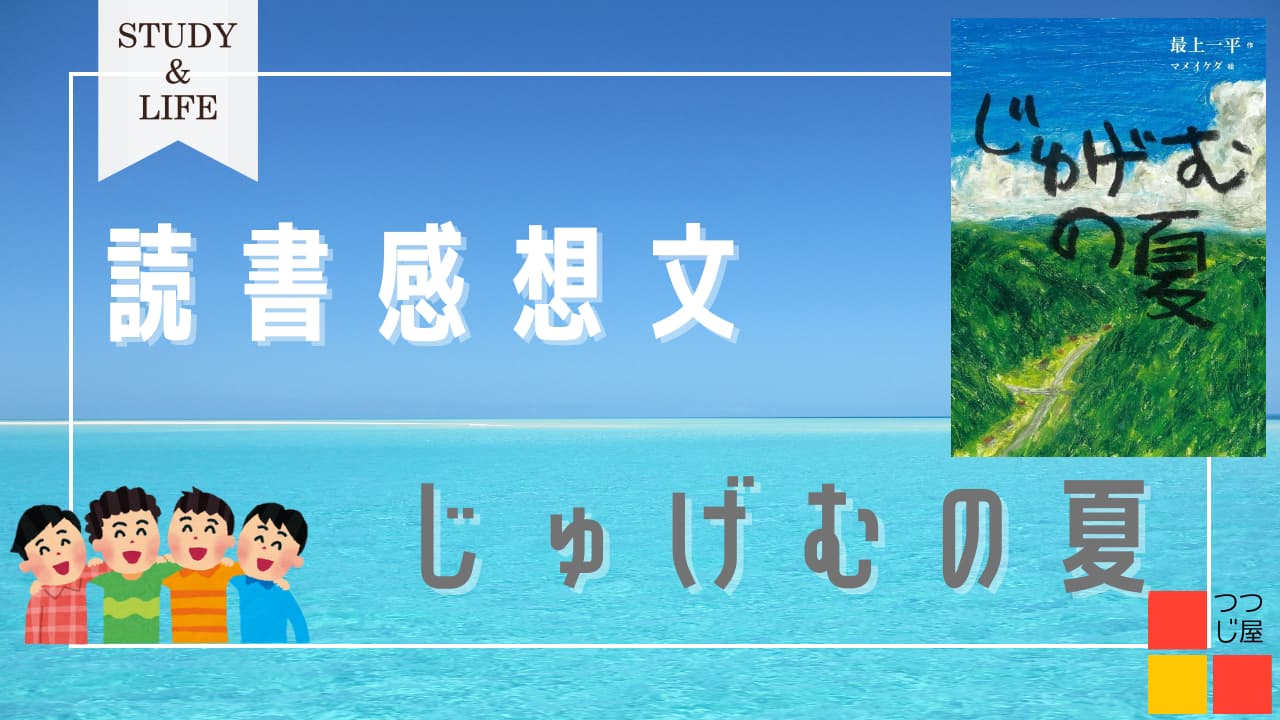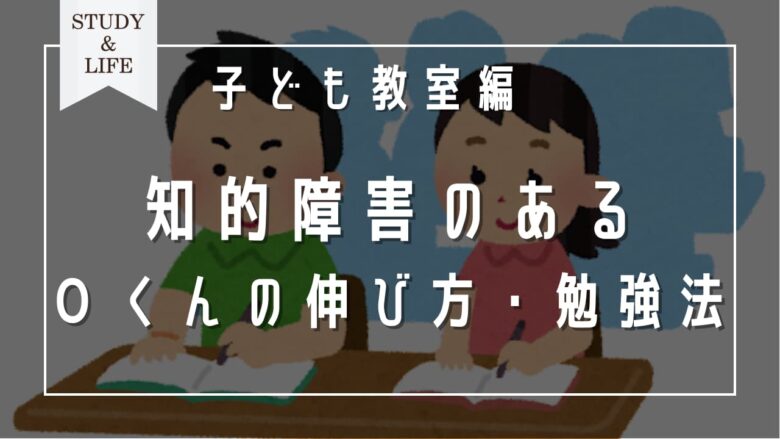知的障害を持つ子どもたちの学びには、特別な工夫が必要ですよね。
今回の記事では、私が運営する子ども教室に通う高校1年生・翔くん(仮名)とのエピソードをもとに、どのようにして学習を支援しているのか、その方法や考え方を具体的にお話していこうと思います。
翔くんは特別支援学校に通いながら、国語や算数といった基礎学力の向上に取り組んでいます。しかし、簡単ではない学習に向き合う中で、”イヤ”と言って投げ出したくなる瞬間も少なくありません。
それでも少しずつ成長を重ねる翔くんの姿から、学びの可能性と支援の大切さを感じ取っていただければと思い記事を書いてみました。皆さんの少しでも参考になればと。

私は地方在住の50代。子どもの教育に関わる仕事を週2回ペースでしている”つつじ屋”といいます。
家族:だんな 定年間近の会社員
長男 大学生 勉強が大好き
次男 大学生 自由が大好き
三男 高校生 ウルトラマン大好き
三男は発達障害グレーゾーンで境界知能の持ち主です。
このブログでは、この三男にまつわるエピソードや困り事などを、グチ多めでつづっていきたいと思っています。よろしくお願いします。
知的障害のある高校生が伸びる学び方 私の教室での実践と工夫
- 今回は私のやっている子ども教室のお話
- 翔くんの現在の学習状況
今回は私のやっている子ども教室のお話
佐藤翔くん(仮名)は令和5年4月から特別支援学校高等部に進んだ高校1年生。
翔くんは、コロナが流行った頃いったん中断したこともありましたが、小学4年生からずっと通ってくれています。
トータル6年間くらいです。
いつもニコニコ、元気いっぱいです。
「せんせー、またどようびあめー!」
と必ず次の雨の予報をしながら入ってきます。

翔くんの現在の学習状況
詳しい診断名などは聞いていませんが、知的障害はあるので、学力は一般の高校生並とはいきません。
算数は小学2~3年生レベル、国語は小学1~2年生レベルの学習をしています。
国語については文章を読むことはできますが、内容を読み取って問題に答えるということは難しいです。ひらがな、簡単な漢字は書けます。算数も2ケタ×2ケタのひっ算がぎりぎりです。2ケタ÷2ケタになると難しい。
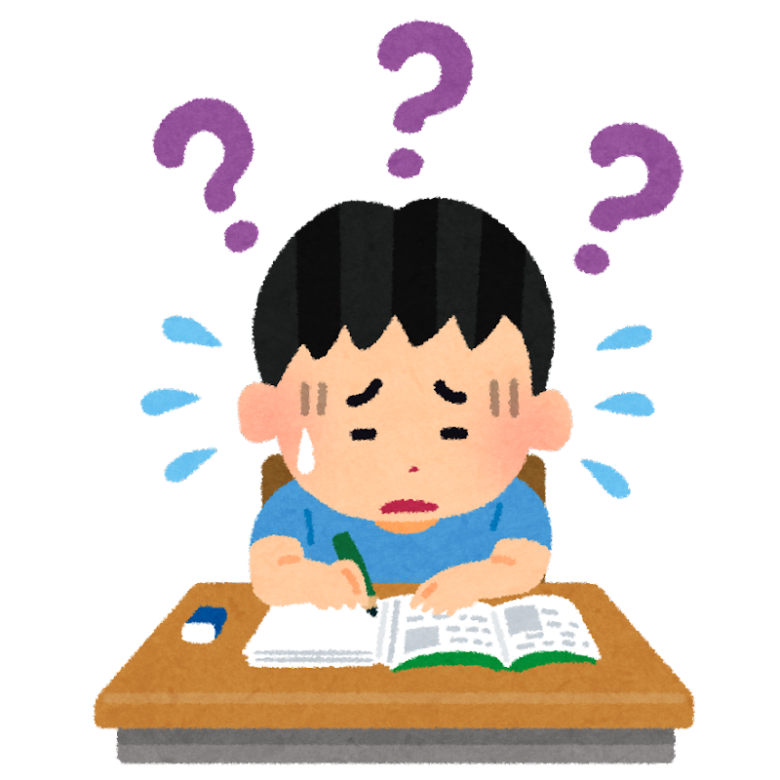
学習が進む工夫と声掛けの方法
- 学力をつけるのは難しい
- 勉強を拒否された時
- まず身近な目標を決める
学力をつけるのは難しい
今の学力をつけるのも簡単ではありませんでした。
同じことを何十回と一緒にやって、本当に一歩一歩進んできました。
お母さんとも相談し、具体的にはどこまでできるようになりたいかも確認しています。お母さんのご希望は、高校生の間に算数も国語も小学校卒業程度の内容ができるように、ということでした。小学校卒業程度の学力といっても、翔君にとってはかなり高い目標です。算数では分数や四則混合の計算、国語ではかなりの長文を読んで内容を理解できなければなりません。
高校1年生の今、算数は割り算、国語は小学校1年生の問題に取り組んでいます。算数は比較的好きみたいですが、国語は文章の内容を読み取ることが難しいようです。漢字は1年生のレベルのものなら書けます。音読することもできます。
当然新しい問題は分かりません。一問ずつゆっくり一緒にやっていても翔くんには分からない時も多いです。いつもはニコニコの翔くんですが、そうなると
「もうやらない!おしまい!いやいや!」
と言って拒否することもあります。
勉強を拒否された時
とはいえ、そこで「ハイ分かった、おしまいね。」としてしまっては進歩がない。
”イヤ”にもレベルがあって、1~10段階で10がMAXとすると、レベル12くらいになったらその日はやめます(10超えてるって)。
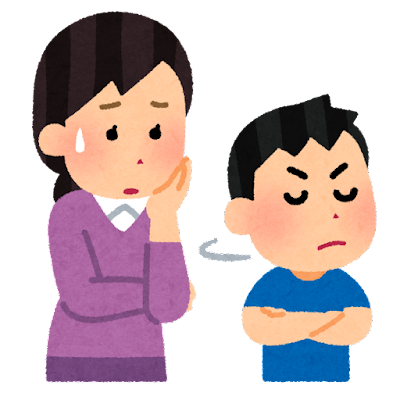
もちろんその日によって翔くんの状態は変わるので一概には言えませんが、レベル10でもほんの少しならできるときもあります。レベル7・8なら絶対やれる。

まず身近な目標を決める
ただこの時、終わりが見えるようにしてあげています。
「このプリント1枚やったらおしまい。」
「このプリントの表面だけやったらおしまい。」
「あと2問やったらおしまい。」
「あと10分頑張れたらおしまい。」
「あと2分頑張れたらおしまい。」
学習がいつ終わるかわからないと、子どもにとっては大きなストレス(苦行)になります。そのため、終わりを具体的に示す・見せるようにして、少しでも安心感を持って取り組めるようにします。

この声掛けも、同じことを言うと翔くんはパターン化してしまう(いやだと言えば2~3問だけで終われると認識してしまう)ので、2問でおしまいと言った次には時間で区切るなど、終われる条件を変えるようにしています。
翔くんの成長と家族の支え
- 通い続けてくれている翔くん
- 社会に出てからの学力
通い続けてくれている翔くん
ずっと通い続けてくれている翔くんと、通わせ続けてくれているご両親。
頑張る翔くんと、少しでもできることを増やして翔くんの将来に役立てたいと願うご両親って、どちらもすごいですよね。
翔くんの進み方はとてもゆっくりです。100人いれば100通りの伸び方があります。伸び方に正解はありません。
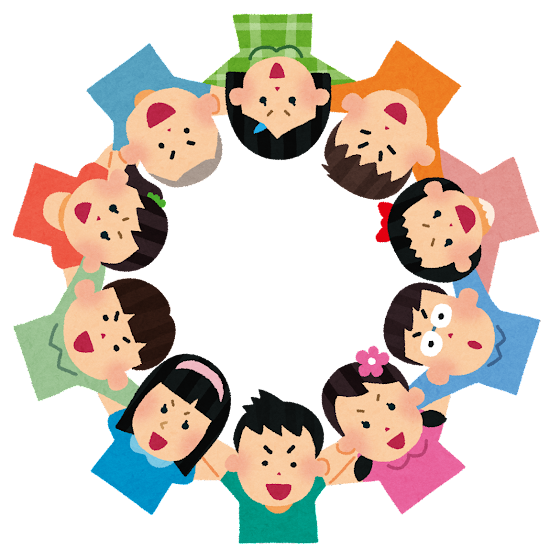
教室で勉強を教えているからには、やはり少しでも学力を伸ばしてあげたいと思います。
学力が伸びることで、高校、大学も”行けるところ”ではなく自分で選ぶことができるようになります。そうなることで将来の働き方の選択肢も広がります。

社会に出てからの学力
それでもいったん社会に出てしまうと、学力は結局あまり関係なくなってしまいます。
長い人生、そこからが本番。
少々の鈍感力だったり、打たれ強さだったり、自分の持っている良さや武器を使って、力強く生きていってほしい。

翔くんの良さは明るさ、繰り返しやれる根気強さ、自分の想いを伝えられる気持ちの強さ。家族に大切にされているからこその心の安定も感じられます。

長い人生における幸せの大切さ
- そしておそらく翔くんは、毎日楽しい
- 知的障害のある高校生が伸びる学び方 私の教室での実践と工夫 まとめ
そしておそらく翔くんは、毎日楽しい
一人で生きていくにはどうしたらいいのかとか、いくらくらいの収入を得ることができるのかとか、問題はもちろんたくさんあります。
そう、そのあたりは多分大問題なのですが、翔くんが幸せなら、うちの三男が毎日楽しく幸せなら、まずは合格ということで・・・。
うちの三男くんはもっとがんばらないといけません・・・。

知的障害のある高校生が伸びる学び方 私の教室での実践と工夫 まとめ
①勉強が”イヤ”になってしまう時もあるが、諦めては進歩が無い。
②”イヤ”にもレベルがある。”イヤ”レベル7・8なら絶対にやれる。
③終わりが見えるようにしてあげる。 具体的には↓
③-1 「このプリント1枚やったらおしまい。」
③-2 「このプリントの表面だけやったらおしまい。」
③-3 「あと2問やったらおしまい。」
③-4 「あと10分頑張れたらおしまい。」
③-5 「あと2分頑張れたらおしまい。」
④この声掛けは、パターン化しない様に終われる条件を変える。

↓こちらは、私が運営している子ども教室についての関連記事です
生まれてから~保育園までのできごと
↓こちらの記事は、生まれて間もないころのお話です。
↓三男が通っている、児童精神科の先生のお話
グレーゾーンの三男にはこんな「あるある」な特徴もありました。
保育園時代に気になっていたことの記事を書いてみました。よろしければお読み下さい。
【発達障害】グレーゾーンの子供のひどいいびきは、アデノイドによる睡眠時無呼吸症かも?治療で劇的改善!発達にも影響!?治療費は?
小学生時代
こちらは小学1年生、小学校でおもらしばかりしていた頃のお話です
小学1年生、勉強やおもらし、のどの手術(アデノイド除去)について書いてます
小学4年、普通級の子どもさんと上手くコミュニケーションが取れなかったお話です。
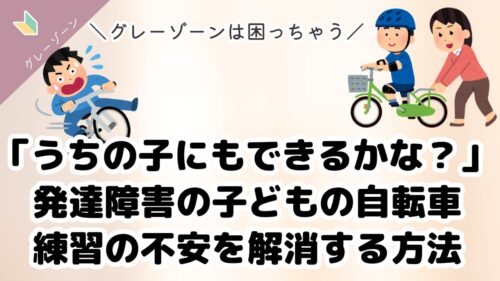
中学生時代
↓療育手帳の取得を申請しても、交付を受けることが叶わなかった時のお話
↓高校(専修学校)入学までの紆余曲折についてお話
↓義務教育の終わりが見えはじめ、将来について考えてたころのお話
↓三男の中学生時代について書いています。(現在、高校生です)
進路と将来
↓中学生になって支援級と普通級のどちらが良いかを考えてみた記事
↓体調の悪さを誰にも伝えられない不安について考えた記事
↓高校(専修学校)入学までの紆余曲折
↓こちらは日本政策金融公庫で借りた学費のお話です↓


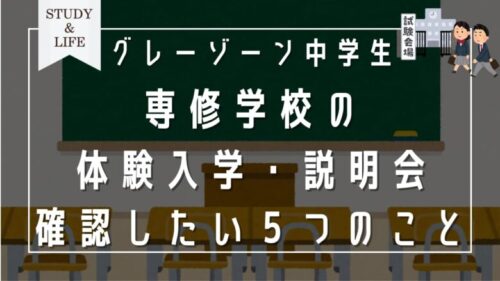
高校生時代
↓こちらは高校(専修学校)へ入学してから初めての中間テストの結果です。
↓こちらは”専修学校各種学校連合会”についての記事です
↓何もできなくてもいい、たまには外へ出てあそんでみよう!↓
↓こちらは発達障害の子供と楽しみたい大阪万博の記事です↓
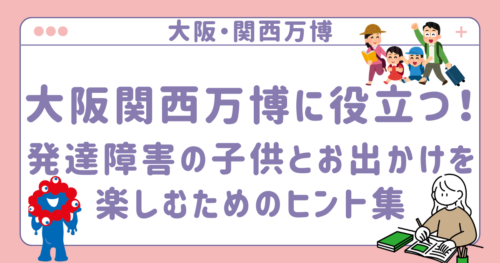
出典:文部科学省公式サイトより