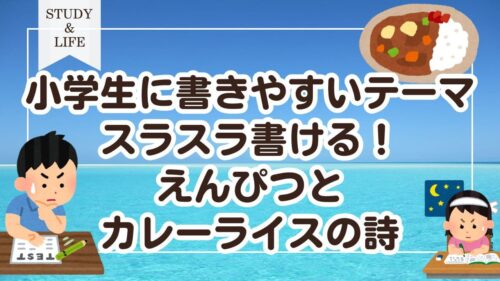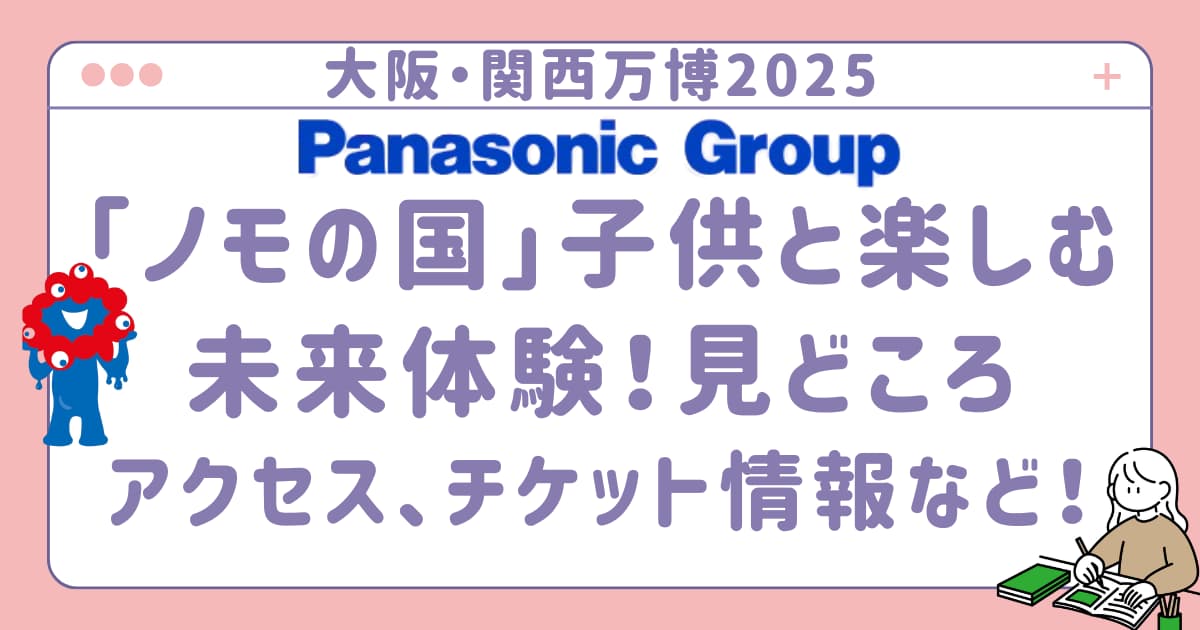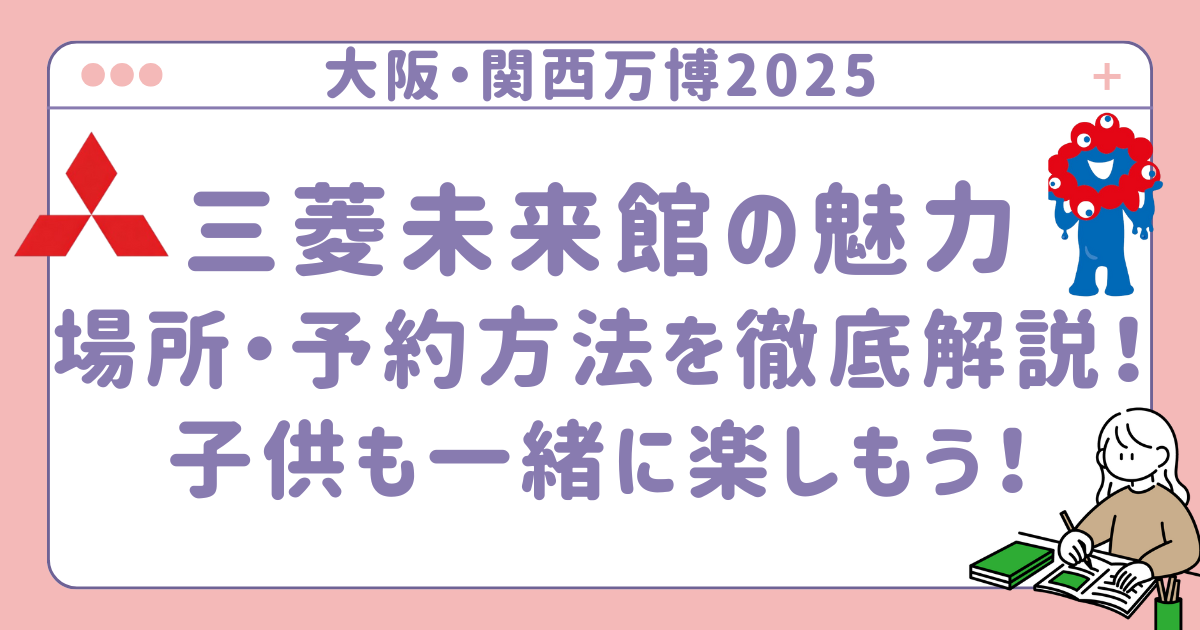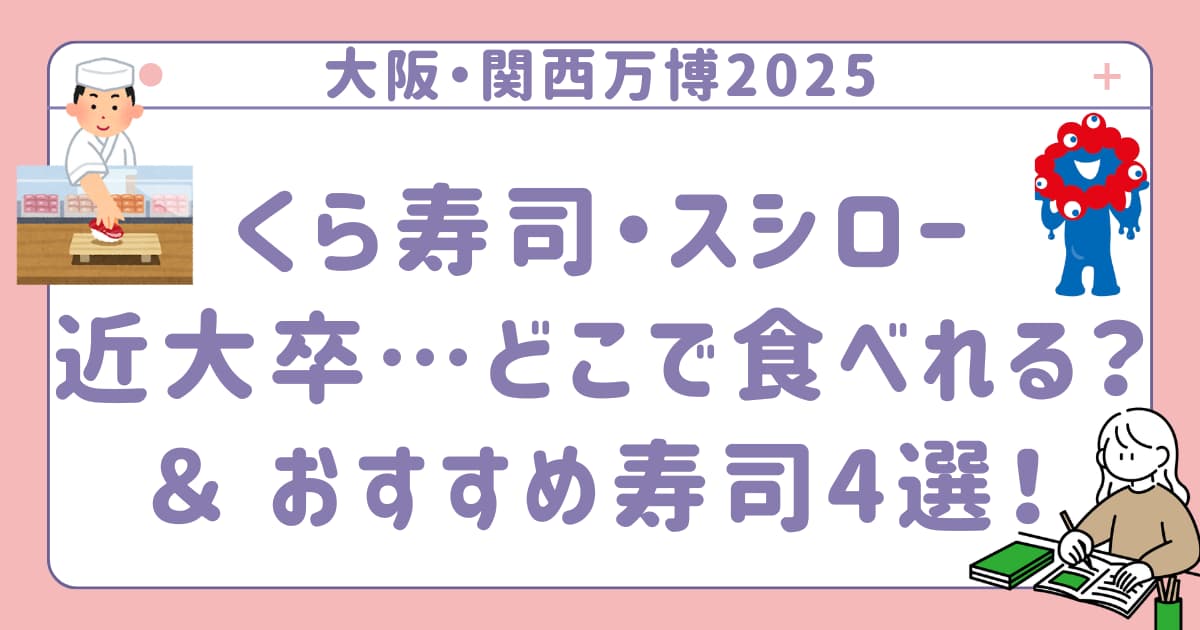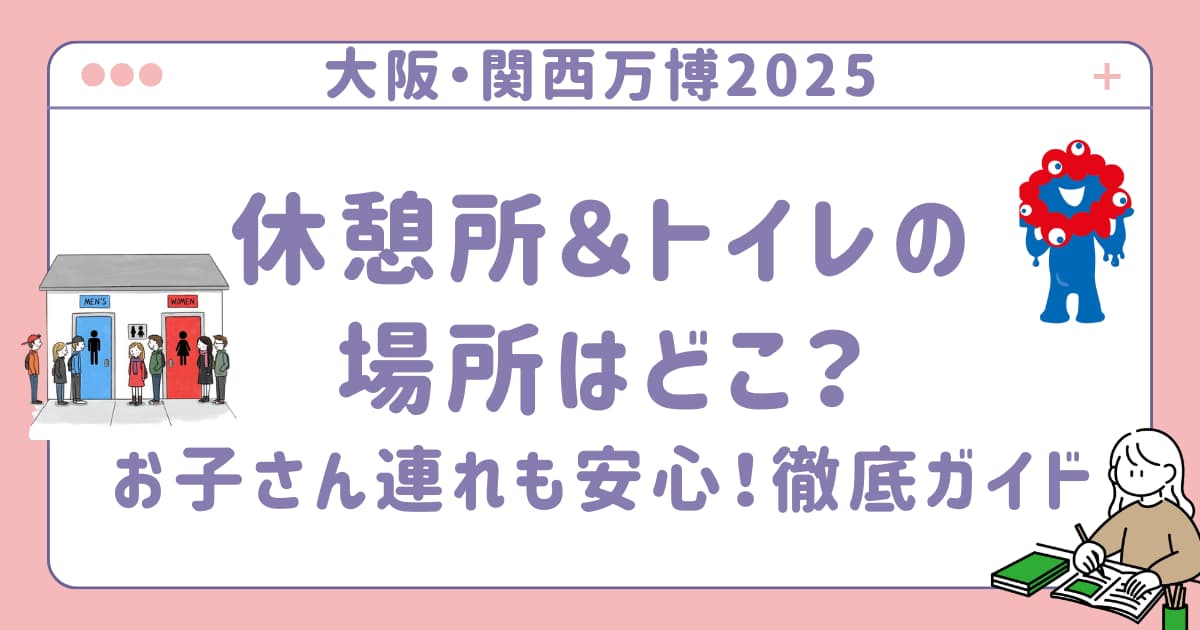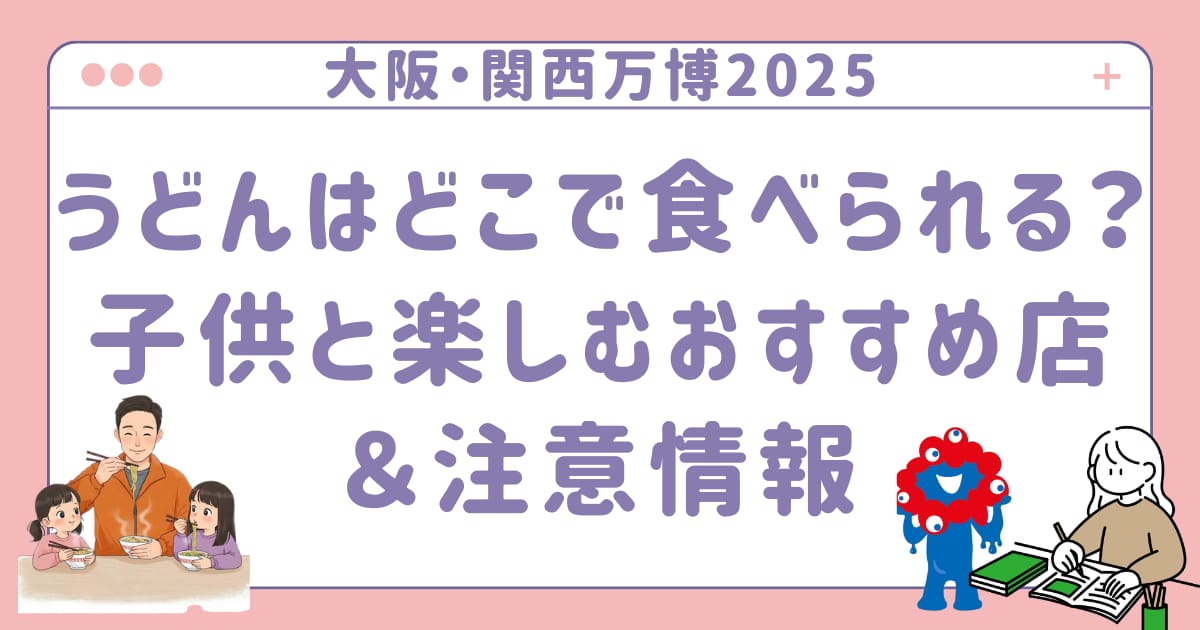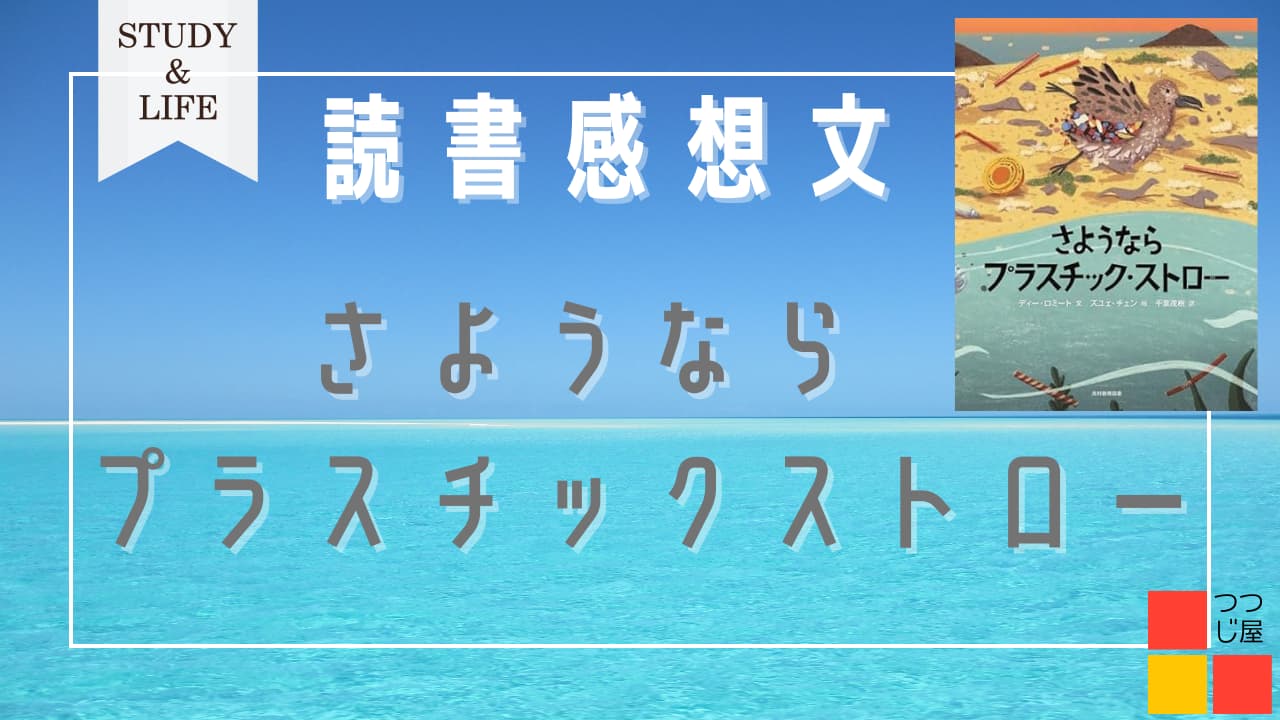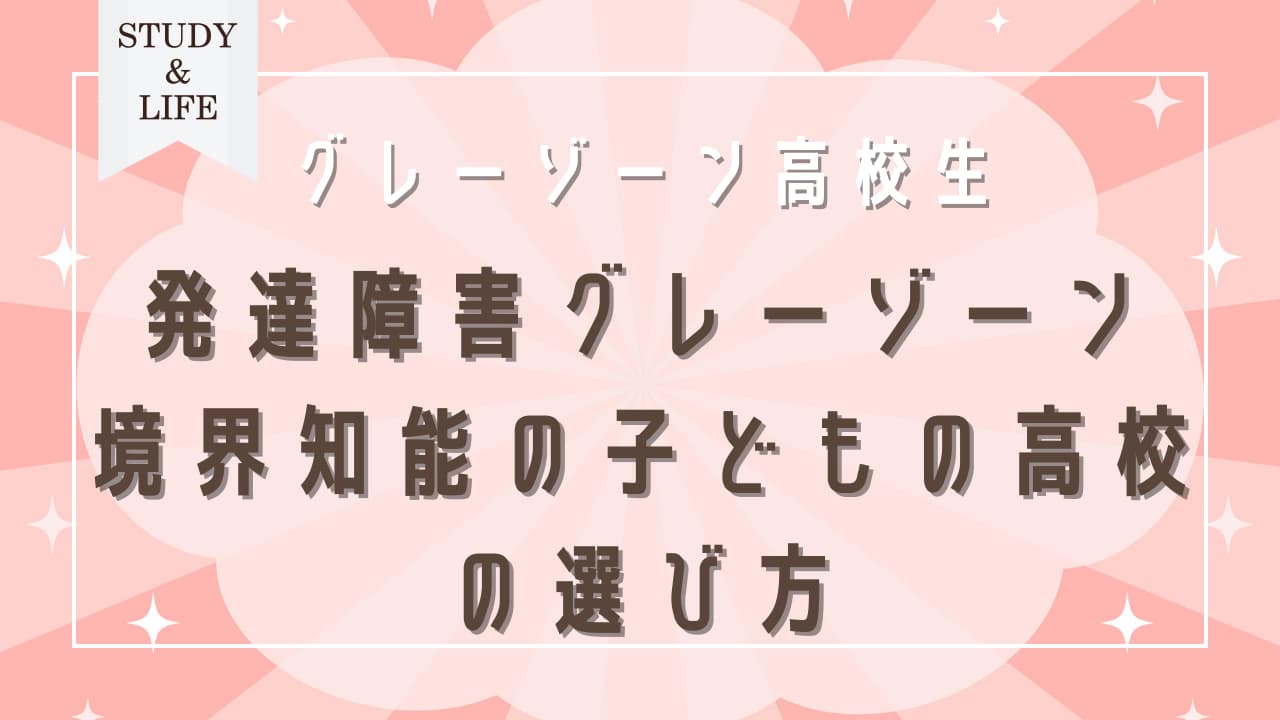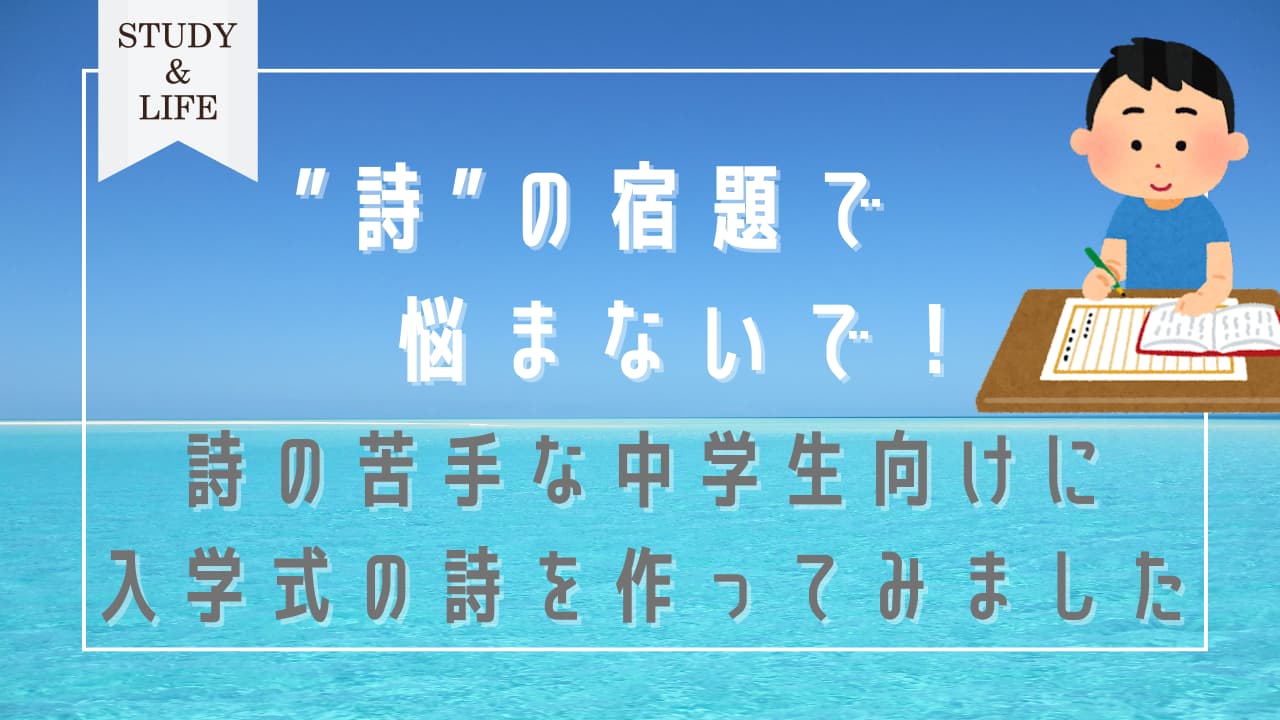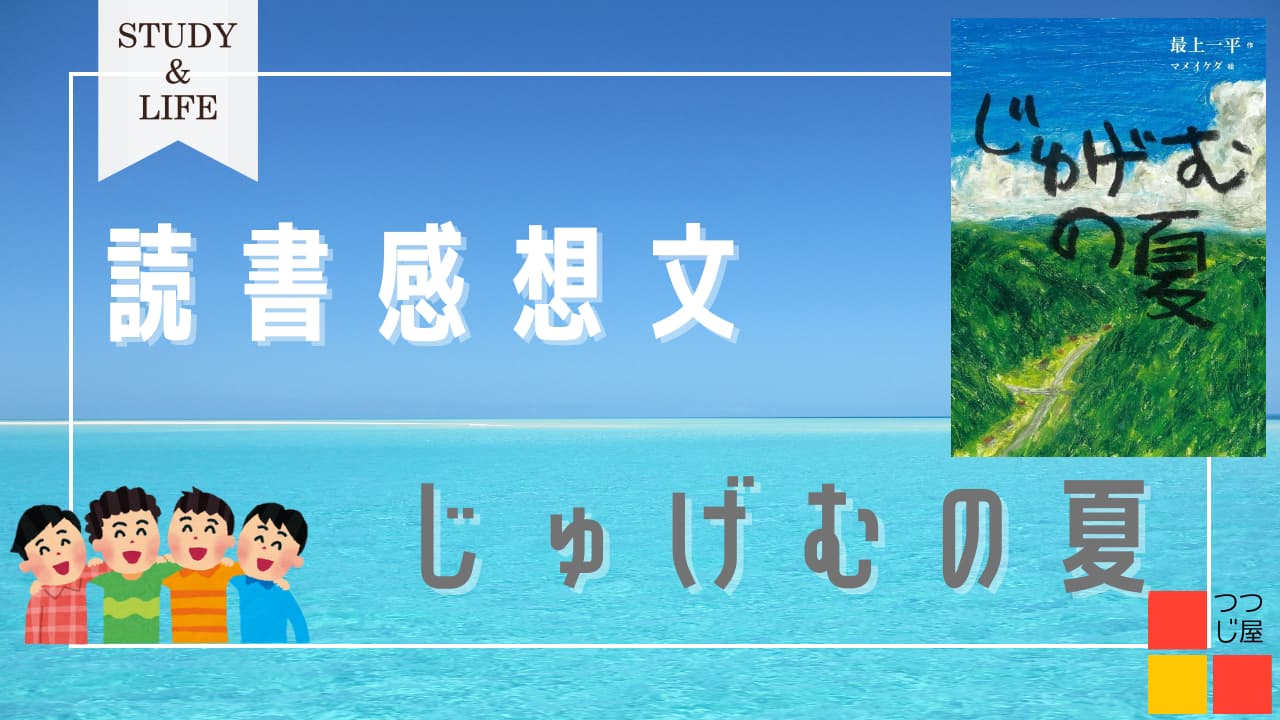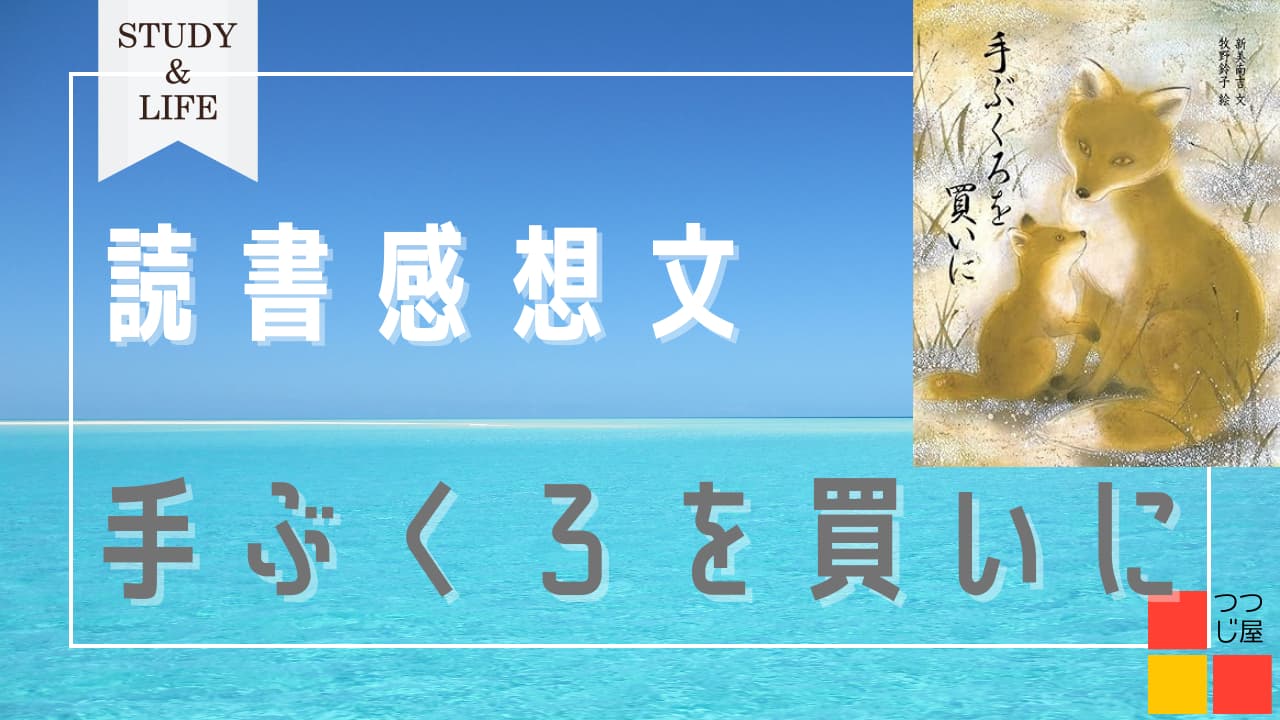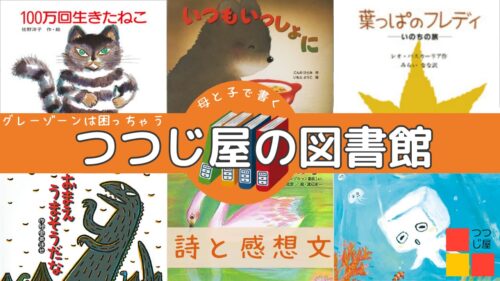今回のお話は『手ぶくろを買いに』。ずっと昔から読まれている、新見南吉の作品です。
雪が積もった冬。お母さん狐は子狐に手袋を買ってあげようと考えます。でもその昔、お母さん狐は人間の町で怖い思いをしており、町へ行くことを躊躇します。
そこで子狐の片方の手を人間の手に変え、必ずそちらの手を出して手袋を買ってくるように伝え、子狐ひとりで町へ行かせます。
子狐は間違えて狐のままの方の手を出してしまいますが、帽子屋さんは手袋を売ってくれました。人間は怖くないと思った子狐は街を歩いてみます。すると仲のいい親子の会話が聞こえてきます。子狐はお母さん狐が恋しくなり、お母さん狐のところへ帰ります。
ほっとするお母さん狐。子狐が手を間違えて出してしまったと聞いて驚きます。そして子狐が「人間ってちっとも恐かないや。」という言葉を聞き、「ほんとうに人間はいいものかしら。」とつぶやきます。
最後のお母さん狐の言葉が深いですね。地球規模的に「お前たち、ちゃんと生きているか。」と言われている気がします。
うちの三男、グレーゾーンボーイです。
私は地方在住の50代の主婦。子どもの教育に関わる仕事を週2回ペースでしている”つつじ屋”といいます。
家族:だんな 定年間近の会社員
長男 大学生 勉強が大好き
次男 大学生 自由が大好き
三男 高校生 ウルトラマン大好き
三男は発達障害グレーゾーンで境界知能の持ち主です。
このブログでは、この三男にまつわるエピソードや困り事を、グチ多めでつづっていきたいと思っています。よろしくお願いします。
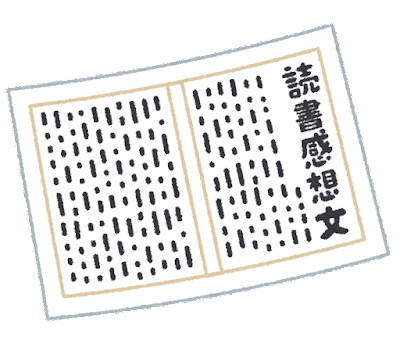
お子さんに本をたくさん読んでもらいたいと思っている親御さんに、絵本定期購読もおすすめです
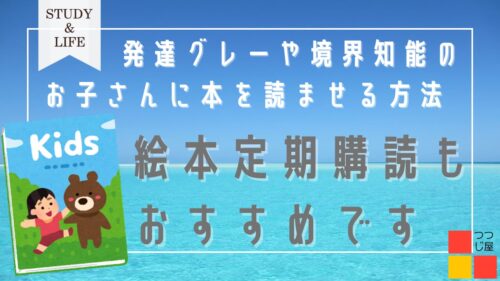
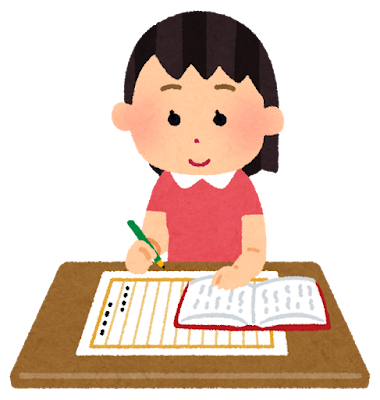
この読書感想文の例文を活用して、文章を「書く価値がある」の?
夏休みといえば頭が痛くなるのが「読書感想文の宿題」ですよね。
親が代筆してまで子どもの読書感想文を手伝う。などは私のグレーゾーンボーイの三男にも行っていました。
じゃあなんで読書感想文なんて書かなければいけないのでしょう。
まぁズバリ言ってしまえば「宿題」だからです。なので難しいことは抜きにして提出しなければならないものはさっさと提出できるように、この読書感想文の例文を活用して下さいね!
また小学生の子どもを持つ親御さんにとって、このブログの読書感想文を使って「書く価値がある」のかもいくつか考えてみました。
1. 子どもたちの参考となる、具体的な読書感想文
この読書感想文により、どのように文章を構成し、どのような内容を盛り込むべきかが明確になるため、子どもが読書感想文を書く際のサポート役として活用することができます。
2.子どもとママのストレス軽減
夏休みの宿題は子どもや親にとって大きなプレッシャーになることがあります。
特に読書感想文は、文章を書くのが苦手な子どもにとっては大きな負担です。子育て世代のママたちは子どものストレスを軽減し、楽しい夏休みを過ごさせたいという気持ちも強いですよね。
3. 忙しいママと子どもの時間を節約
忙しいママや子ども(子どもは暇かな?)にとって、読書感想文の書き方やアイデアを一から考えるのは大変です。
このブログに掲載された読書感想文を参考にすることで、時間を節約し、効率的に宿題を進めることができますよ。皆さんも時間を節約するために、このブログに訪れるかたも多いのではないでしょうか!
この読書感想文のブログ記事を掲載することで、多くのパパ・ママの手助けができ、子どもたちの学びがより充実したものになると考えています。
私の読書感想文が多くのパパ・ママにとって貴重な情報源となることを願っています。

読書感想文『手ぶくろを買いに』 あらすじと伝えたいこと
- 読書感想文『手ぶくろを買いに』 例文
- 新美南吉の紹介と生い立ち
- 「てぶくろを買いに」は何歳向けですか?
- 「てぶくろを買いに」の舞台はどこですか?
- 「手ぶくろを買いに」は何年生の教科書に載っていましたか?
読書感想文『手ぶくろを買いに』 例文
↓フレーベル館さん(アマゾンヘ)↓

この本のさいごにでてくる
「ほんとうににんげんはいいものかしら。ほんとうににんげんはいいものかしら。」
というおかあさんぎつねのことばがとても心にのこりました。
きつねやほかのどうぶつからは、にんげんってどういうふうにみられているのかな。
きけんだっておもわれているのかな。こわいっておもわれているのかな。
このおかあさんぎつねはにんげんのことをとてもこわがっています。むかしこわいめにあったからしかたないです。
でも、わたしたちにんげんがこわいそんざいなんだっておもわれるのは、すこしざんねんです。
こぎつねに手ぶくろをかってあげようとまちまでいくけれど、おかあさんぎつねはこわくてまちの中へ入れません。
子ぎつねはひとりでまちへいきます。でもまちがえて、きつねのままのほうの手をだしてしまいます。ぼうしやさんはとてもびっくりしたとおもいます。
でもおいかえしたりはしませんでした。子ぎつねがぶじに手ぶくろをかえてよかったです。
でも、おかねがほんものだったから手ぶくろをうってあげたけど、木のはでつくったにせものだったらやっぱりうってあげなかったのかな。
にせもののおかねだったら、うってあげなくてもしかたないかなとおもいます。ぼうしやさんも、ちゃんとうれないとせいかつがくるしくなるからです。
そうしたら子ぎつねは、にんげんのことをいじわるだとおもうのかな。
にんげんにしてみれば、おかねがないならうってもらえないのはあたりまえだけど、きつねにとってはそうじゃないかもしれません。
子ぎつねはにんげんはこわくないとおもったので、まちの中をみてあるきます。
しらないところをひとりであるきまわるなんて、わたしだったらできません。それこそこわいひとがいるかもしれません。子ぎつねはゆうきがあるなとおもいます。
でも、手ぶくろをうってもらえなかったら、きっとすぐにおかあさんのところへかえっていたとおもいます。
「おかあさんのいっていたとおり、にんげんはこわいんだ。」
っておもって、あわててにげたとおもいます。さいしょにあったにんげんのぼうしやさんがやさしかったから、子ぎつねもたんけんするきもちになれたんだとおもいます。
こぎつねがあるいていると、にんげんのおかさんがうたうこもりうたがきこえてきます。
なかのいいおやこのかいわをきいて、こぎつねはおかあさんがこいしくなっていそいでかえります。
おかあさんぎつねはにんげんはこわいとおもっていたのだから、子ぎつねのことがとてもしんぱいだったとおもいます。
子ぎつねをひとりでいかせたことを、こうかいしていたかもしれません。子ぎつねはよりみちしていたから、おかあさんぎつねがおもっていたよりかえってくるのがおそかったはずです。
だから、にんげんにつかまってしまったのでは、としんぱいでたまらなかったとおもいます。
にんげんのおかあさんもきつねのおかあさんも、子どものことがだいすきでたいせつなんだとおもいます。
きつねにはきつねのせいかつがあって、にんげんにはにんげんのせいかつがあります。
ちがうところはたくさんあるとおもうけど、かぞくがいて、みんなでなかよくくらしたい、とおもうのはいっしょだとおもいます。
おかあさんぎつねがすこしでもにんげんはいいものだとおもってくれたらうれしいです。
大切なこと 生成AI編
「読書感想文」を書くためには、まずは本(本物:現物・電子書籍)を一度は読んだ方がよいですね。
皆さんにこの「読書感想文」の記事を参考にして頂けることは、大変ありがたいと思っています。
しかし、本(本物)を読まずに、この読書感想文の記事(ある意味贋作:偽物)だけをたよりに文章を書けば、皆さんの書く読書感想文の内容がチグハグになってしまうからです。
実際に皆さんもたくさんの読書感想文のブログ記事を見ながら、読書感想文を書こうと思っているのではないでしょうか。
そして危険なのが、グ-グルのランキング(5位以内)に入るような読書感想文の記事でも、間違いが書いてあることです。
まあ、実際に本を読めばその読書感想文の記事が間違っているのが分かるのですが、もう書いてあることがデタラメです。
ひどい記事になると作者や主人公の名前自体が違ってますし、主人公がとった行動も違います。また架空の人物を作って物語に出演させたりもしています。
学校の先生に見せたら「何の本を読んだの?」と言われちゃいそうです。
こういった間違いが書いてある読書感想文は、初期の生成AIで書いたのでしょうね。皆さんも生成AIで読書感想文を書くときは注意しましょう。(最新AIは結構正確です)
ですから図書館で借りればOKですので、必ず本(本物)に触れて、読んでから読書感想文を書くことが大切です。
そして本をかる~く読んだら、チャットGPTを使い読書感想文を書いてみましょう。
そうすればAI風の?最強の読書感想文が出来上がります。新しい道具も上手に使っていきましょう!このサイトの読書感想文(例文)はチャットGPTは使用していませんが、生成AIの学習には利用されていました…。(微妙)
もちろん自分の頭で考えるのが、無敵なのは言うまでもありませんね!

新美南吉の紹介と生い立ち
「ごんぎつね」の作者は新美南吉(にいみ なんきち)です。彼は1913年に愛知県知多郡半田町(現在の半田市)で生まれました。本名は新美正八(にいみ しょうはち)といいます。
太平洋戦争の30年ほど前に生まれた方ですから、作者の幼少期はすこし複雑な家庭環境となっています。
4歳の時に母親を亡くし、8歳で母方の実家である新美家の養子に出されました。しかし、養子先での生活に馴染めず、再び実家に戻ってしまいました。
しかし作者の少年時代は孤独でありながらも、文学への興味を深める時間でもありました。
中学時代から童話や童謡の創作を始め、数多くの作品を発表しています。中学を卒業した後、東京外国語学校英語部文科に進学し、児童文学作家としての道を歩み始めています。
新美南吉は、結核により29歳の若さで亡くなりました。
食糧事情も悪かったのでしょう。彼は1934年に初めて喀血(かっけつ)を発症し、その後も病状が悪化していきました。特に晩年には喉頭結核が進行し、1943年3月22日に愛知県半田市の実家で息を引き取りました。
とてもつらい病魔と闘いながらも創作をし続けたことから、作者の文学への熱い気持ちが伝わってきます。
「ごんぎつね」は、作者が19歳の時に発表した作品で、彼の代表作の一つです。この物語は、孤独な小狐ごんと村人兵十との交流を描いており、物語を読んだあとに読者の胸にぐっとこみ上げてくるものがあります。
また作者は、児童文学作家として知られ、「ごんぎつね」以外にも「手袋を買いに」や「おじいさんのランプ」などの作品を残しています。
彼の作品は、シンプルでありながらも深い感情を描き出すことで、多くの読者に愛され続けています。
「てぶくろを買いに」は何歳向けですか?

新美南吉の「てぶくろを買いに」は、主に小学校3年生から4年生(9歳〜10歳)向けの童話作品です。
この物語は、母親を亡くした狐の子どもが、寒い冬に人間の店に手袋を買いに行くという心温まるお話です。優しく分かりやすい言葉で書かれていますが、その中には深いメッセージが込められているんです。
小学校低学年の子どもでも、お母さんを思う気持ちや、寒い中での買い物の大変さなど、物語の基本的な部分は理解できます。一方で、高学年になると、親子の絆や命の大切さ、思いやりの心といった、より深いテーマも感じ取ることができます。
また、擬人化された狐が主人公という設定は、子どもたちの想像力を豊かにしてくれます。人間社会で生きる動物という視点から、差別や偏見についても考えるきっかけを与えてくれる作品です。
このように、読む年齢によって異なる発見や学びがあるため、小学生全般(6歳〜12歳)に適した作品だと言えます。特に道徳の授業などでよく取り上げられ、教育的な価値も高い童話として評価されていますね。
「てぶくろを買いに」の舞台はどこですか?

新美南吉の「てぶくろを買いに」の舞台について、かんたんに説明させていただきます。
この物語の舞台は、愛知県半田市(当時の愛知県知多郡半田町)です。新美南吉さんが実際に住んでいた場所なんです。
特に大きな出来事が起こる場所は、お母さんキツネと子ギツネが暮らす山と、てぶくろを売っているお店がある町です。山は半田市の郊外にある小高い丘で、当時は木々が生い茂る自然豊かな場所でした。
お店のある町は、半田の商店街がモデルだと考えられています。昔の半田は、醸造業で栄えた港町で、たくさんのお店が並ぶにぎやかな街並みがありました。
今でも半田市には「新美南吉記念館」があり、作品の舞台となった風景や、南吉さんの生活を知ることができます。冬の寒い日に、小さな子ギツネが町へてぶくろを買いに行くという心温まるお話は、この半田の町から生まれたのです。
「手ぶくろを買いに」は何年生の教科書に載っていましたか?

新美南吉の「手ぶくろを買いに」は、長年にわたって小学校3年生の国語の教科書に掲載されていました。
この物語は、1954年から2011年まで、小学校3年生の国語の教科書の下巻に採用されていました。つまり、約57年間も教科書で学ばれ続けた人気の作品なんです。
多くの場合、3年生の2学期の後半か3学期に学習されていました。冬の季節にぴったりのお話だからかもしれませんね。
ただ、2005年頃からはだんだん教科書での扱いが少し変わってきたようですね。参考程度に掲載されたり、巻末に近いところに載せられたりするようになりました。
でも、「手ぶくろを買いに」は今でも多くの人に愛される童話です。教科書以外でも、絵本や児童書として今でも書店で見かけることができまね。
『手ぶくろを買いに』で伝えたいこと
- 人間・動物に関わらない親子の愛情
- 経験によって物事の見え方は変わる
- いいもの・わるいものの判断は難しい
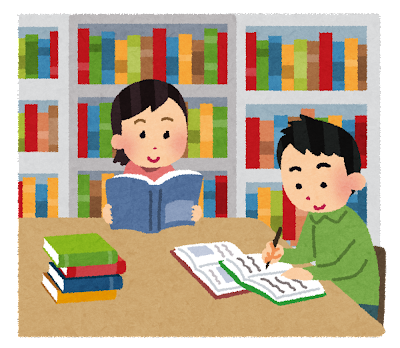
人間・動物に関わらない親子の愛情

私たち人間には親は子を愛し、子は親を慕う、親子間の愛情のやり取り、絆が存在します。しかしそれは人間に限ったことではありません。
狐にとっても子どもはかけがえのない存在であり、母親を恋しく思う気持ちもあります。これはほとんどの動物で言えることです。どんな動物も自分の子どもは必死で守ります。
人間から見たら”きつね”は”きつね”でしかないのですが、きつねの世界では大切な子どもであり、恋しい母親です。人間中心で考えがちですが、生命すべてに対してリスペクトする気持ちが大切です。
経験によって物事の見え方は変わる

お母さん狐にとって人間は怖い存在。それは昔、友達の狐が人間に追いまくられて、命からがら逃げたことがあったからです。狐だと分かってしまったら、捕まえられて檻に入れられる、と思っています。
一方の子狐は初めての人間が帽子屋さんです。間違えて狐のままの方の手を出しても、手袋を売ってもらえたし、捕まることもありませんでした。人間の親子の優しいやり取りも聞き、人間は怖くない、と考えます。
お母さん狐は子狐が人間はそんなに怖くない、というのを聞いて、自分の考えに疑問を持ち始めます。物事は人によって、その経験によっていろいろな見え方をするものです。「そんなはずはない。」と拒否するのではなく、いろんな考え方を取り入れていきたいですね。
いいもの・わるいものの判断は難しい

前述の考えと少し似ている内容です。
帽子屋さんは子狐にとっては”いいもの”でした。狐だと分かってしまっても、手袋を売ってくれたし、捕まえられることもなかったからです。
でも帽子屋さんは本当に優しいいい人間だったのでしょうか。帽子屋さんは子狐が持ってきたお金を、木の葉ではないかと疑っていました。しかしお金が本物だったので、売ってあげたのです。帽子屋さんにしてみれば、商売が成り立てばいいわけです。
お金が偽物だったら売らなかったはず。だからといって手袋を売らなかった帽子屋さんが悪いわけではありません。人間の世界では当然のことです。でもこぎつねにしてみれば「人間はいじわるだ。」ということになるでしょう。
お母さん狐が最後に「ほんとうに人間はいいものかしら。」と考えを巡らせているように、いいもの、わるいものの判断は難しいのです。
↓いろんな本にふれる機会があるといいですね! ↓
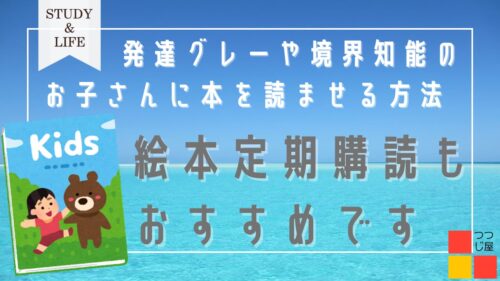
今回も400字詰め原稿用紙3枚分です。(1200文字)
新見南吉は「生存所属を異にするものの魂の流通共鳴」というテーマを生涯かけて追求したそうです。(偕成社『手ぶくろを買いに』表紙裏の言葉より)なんだか難しい日本語ですね。私的には「地球上のありとあらゆる生命はみな兄弟」ということなのかなと解釈しています。地球は人間だけのものではないですからね。
お母さん狐に「ほんとうに人間はいいものだった。」と思ってもらえるよう、少し自分自身を振り返りながら、おごらず、謙虚さを忘れずに過ごしていけるといいなと思います。

お子さんに本をたくさん読んでもらいたいと思っている親御さんに、絵本定期購読もおすすめです 〉〉
↓こちらはグレーゾーンの子どもに向けて書いた読書感想文と詩の一覧です。
↓ここから下は夏休みの読書感想文です
出典 文部科学省 これからの時代に求められる国語力について
↓こちらはグレーゾーンの子どもに向けて書いた読書感想文と詩の一覧です。
↓こちらは夏休みの詩の宿題です